土筆のホームページ
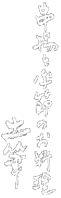
基本営業時間
昼11:00〜14:00
夜17:00〜21:00
定休日
毎週水曜日、及び第三木曜日
座席
カウンター6席
座敷12席
駐車場
7台(送迎可/要予約)
ご予約
042−972−7886
住所
埼玉県飯能市笠縫272




初夏〜夏の食彩
「べっこうしじみ」〜二枚貝綱マルスダレガイ目シジミ科〜
淡水と海水の混り合う宮城県、北上川の砂地で獲れる「ヤマトシジミ」が「べっこうしじみ」と呼ばれます。べっこう色した2センチほどの大つぶのシジミで、なにしろ特有のクセがなくて味噌汁になどすればスゥー飲めて、身もまた旨い。「上品なシジミ」といったところでしょうか。六月から十月が漁期ですが、旬は「夏」です。栄養抜群で肝臓にもいい、夏バテにもってこい!


「白貝」〜二枚貝綱マルスダレガイ目ニッコウガイ科〜
サラガイ、ベニザラガイ、アラスジサラガイは総じて「白貝」と呼ばれています。サラガイが他の二種よりやや小さいという事以外はほとんど同じと思ってよいと思います。日本海側では「まんじゅうがい」、「満珠貝」などと呼ばれとてもポピュラーな貝です。刺身や焼き貝、煮貝にします。刺身はまったくといっていいほどクセはなく、ほのかに甘く、うまい!


(能登の白貝「アラスジサラガイ」10cm程) (二つの貝柱と身を刺身にします。)

「イタヤ貝」〜二枚貝綱カキ目イタヤガイ科〜

「トリ貝」〜二枚貝綱マルスダレガイ目ザルガイ科〜

「石垣貝(イシガキガイ)」
〜二枚貝綱マルスダレガイ目ザルガイ科〜
「揚巻貝(アゲマキガイ)」
〜二枚貝綱マルスダレガイ目ナタマメガイ科〜


「べっこうしじみ」〜二枚貝綱マルスダレガイ目シジミ科〜
淡水と海水の混り合う宮城県、北上川の砂地で獲れる「ヤマトシジミ」が「べっこうしじみ」と呼ばれます。べっこう色した2センチほどの大つぶのシジミで、なにしろ特有のクセがなくて味噌汁になどすればスゥー飲めて、身もまた旨い。「上品なシジミ」といったところでしょうか。六月から十月が漁期ですが、旬は「夏」です。栄養抜群で肝臓にもいい、夏バテにもってこい!


「白貝」〜二枚貝綱マルスダレガイ目ニッコウガイ科〜
サラガイ、ベニザラガイ、アラスジサラガイは総じて「白貝」と呼ばれています。サラガイが他の二種よりやや小さいという事以外はほとんど同じと思ってよいと思います。日本海側では「まんじゅうがい」、「満珠貝」などと呼ばれとてもポピュラーな貝です。刺身や焼き貝、煮貝にします。刺身はまったくといっていいほどクセはなく、ほのかに甘く、うまい!


(能登の白貝「アラスジサラガイ」10cm程) (二つの貝柱と身を刺身にします。)

(貝表面の筋がはっきりしていて内側がオレンジががっている事から「アラスジサラガイ」と思われる。)
「イタヤ貝」〜二枚貝綱カキ目イタヤガイ科〜
「イタヤ貝」はホタテ貝の仲間です。大きさはホタテ貝の半分ぐらいで、形、味ともによく似ています。しかし漁獲量は少なく、養殖がほとんどです。また、市場には殻付きで入ってくることは皆無といってよく、剥き身の状態ではいってきます。刺身でもよいのですが土筆ではもっぱら串揚にしてお出ししています。おいしいですよ!

(北海道のイタヤ貝)
「トリ貝」〜二枚貝綱マルスダレガイ目ザルガイ科〜
この貝は殻をはずして茹でた状態のものがほとんどですが、やはり殻付きの生きたものが最高です。この食感と甘味はたまりません。まったくくせもなく、臭みもないので貝の嫌いな方でもきっと「うまい!」と感じられるとおもいます。

(千葉のトリ貝)
「石垣貝(イシガキガイ)」
〜二枚貝綱マルスダレガイ目ザルガイ科〜
標準和名を「エゾイシカゲガイ」といいます。「イシカゲガイ」を「イシガキガイ」と間違ったところから「石垣貝」と表記されるまでに至ってしまいました。天然国産ものは極めて少なく、まして殻付きとなると皆無といっていいほどです。しかし、近年は養殖に成功し、岩手県他、東北各地で養殖されて出荷されています。又、韓国などからも殻をむいた生の状態で入ってきます。トリ貝によく似ていて、おすし屋さん等ではトリガイの代用品として使われてきました。トリガイと違って、その身の色はクリーム色がかっています。トリ貝よりも肉厚で甘味、旨味も十分にあり、くせもないので貝類が苦手な方でも好きになれると思います。
(国産の殻付き石垣貝) (生きているので歯ごたえが!)
「揚巻貝(アゲマキガイ)」
〜二枚貝綱マルスダレガイ目ナタマメガイ科〜
輸入物が多く、国産の「アゲマキ貝」はとても少ないのですが夏頃が旬といえます。煮たり、焼いたりして食べますが、土筆では茹でて酢味噌で。旨味甘味も格別で美味しいですよ!

(愛知のアゲマキ貝)
「大あさり」〜二枚貝綱マルスダレガイ目マルスダレガイ科
その名の通り、大きさが10センチ程のアサリといった感じです。貝柱もかなり大きく煮たり、貝ごと焼いたりします。通常のアサリ同様、硬くなりますが、またその食感がいいのです。
標準和名は「ウチムラサキ」といいます。これは貝の内側が紫色をしている事から。
標準和名は「ウチムラサキ」といいます。これは貝の内側が紫色をしている事から。

(大あさりの佃煮)


