土筆のホームページ
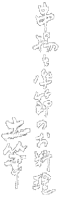
基本営業時間
昼11:00~14:00
夜17:00~21:00
定休日
毎週水曜日、及び第三木曜日
座席
カウンター6席
座敷12席
駐車場
7台(送迎可/要予約)
ご予約
042-972-7886
住所
埼玉県飯能市笠縫272




春を先取り!冬の食彩
「冬の真鯛(まだい)」~スズキ目タイ科~
一般的には真鯛の旬といえば春の桜の頃に体色が紅色になる「桜鯛」の時期です。産卵の為に栄養を蓄えるこの時期の魚は通常、卵や白子にとられ身はまずくなるものですが、「真鯛」は卵、白子が身に対して小さいので、身に十分な栄養が残り、逆に旨くなるのです。しかしながら、ほんとうに美味しいのは「冬の真鯛」なんです。脂がしっかりと乗っていながら身がしまって旨味が凝縮され、甘みもまし、噛めば噛むほどにうまい。そうなんです!今が旬なんです!寒さも厳しい1月、2月に「真鯛」で春の気分を先取りしましょう!

(豊後水道のマルキの「冬の真鯛」)
「鰊(にしん)」~ニシン目ニシン科~
「ニシン」は北の代表的回遊魚で、春をつれて来る魚という事で「春告魚」とも記されます。
又、江戸時代に米のとれない蝦夷地では米の代わりに年貢として納められていて「魚にあらず」
ということで「鯡」とも書きます。語源は、身を二つに裂いて食用にすることから「二身」と
する説が有力です。「ニシン」といえば「数の子」ですが、アイヌ語でニシンの事を「カド」
といい、「カドの子」がなまって「かずのこ」になったようです。「ニシン」の旬は、子を持ち始める冬から春です。刺身でよし、塩焼きもまたうまい!「土筆」では串揚にしたりします。


北海道の「ニシン」(数の子を取り出したところ) ニシンの刺身
「公魚(わかさぎ)」~サケ目キュウリウオ科~
元々は海産魚であったこの魚は、その卵が非常に丈夫で移植が容易なことから、淡水湖へ移植され、今ではすっかり「淡水のワカサギ」となってしまいました。淡水魚の割にはEPAやDHAが豊富で、頭から丸ごと食べれるのでカルシウムもしっかり補給でき、健康食品としての価値は高いようです。「ワカサギ」の旬は冬から春先です。2月にもなると卵を持つものも現れ、その味は淡白で繊細。ふっくらとしていて口に残らない。フライにすればお子様でもパクパクいけます。しかし、本来の味を楽しむなら、一夜干したものを焼いてガブリ!キュウリウオ系のほのかな香りと繊細なうまみが感じられ・・・うまいんです!!


「琵琶湖のワカサギ」 「網走湖のワカサギ」
P.S.江戸時代、霞ヶ浦あたりを治めていた麻生藩が、時の将軍家斉公に「ワカサギ」を献上していたことから公儀御用の魚、「公魚」と呼ばれるようになったようです。

「わかさぎのフライ」
北海道周辺には「ワカサギ」とウリふたつの「チカ」という魚がいます。その違いは、「チカ」は海で獲れ、湖では獲れないという事。そして「チカ」は 腹ビレが背ビレよりうしろ、「ワカサギ」は腹ビレが背ビレより前についてるという点です。味もよく似ていますし、北海道では「チカ」も「ワカサギ」もすべて「チカ」と呼ばれているので「ワカサギ」のつもりで「チカ」を食していることも あるはずです。
(北海道広尾のチカ)

