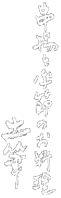




秋の食彩
「甘鯛(あまだい)」~スズキ目アマダイ科~
「甘鯛」又は「尼鯛」と書きますが「メダイ」、「キンメダイ」等と同様、鯛の仲間ではありません。秋から冬が旬のこの魚は、漁獲量で言うと山口県と長崎県が一位、二位を競います。その身は脂肪が少なく、柔らかいのでしばしば焼物、揚げ物、蒸し物などにされます。また一夜干も美味しいです。そして頭の皮目のゼラチンは絶品です。しかしながら鮮度が良ければ「刺身」が旨いんです。特に「やまぐちの甘だい」はブランド化され薄紅色の刺身の評判が高いのです。

(山口県、仙崎のアマダイ)
「半天然子持ち鮎」~サケ目アユ科~
8月下旬から9月にかけて卵を持ち始めた鮎を「子持ち鮎」といいます。養殖ものがほとんどですが養殖技術は発達していて天然に程近いものがつくられています。これが「半天然」とか「天然仕立て」などといわれて売られています。味も香りも脂の乗りも天然と差はないが、顔だけは養殖特有の「あほづら」をしています。


(和歌山の半天然子持ち鮎) (これが噂の「あほづら」)
「鰤(ぶり)」~スズキ目アジ科~
言わずと知れた出世魚の代表格「ブリ」。夏に北上していたものが秋に南下し始めます。そして冬には脂がたっぷりと乗った「寒ブリ」になるのですが、この南下し始めの「秋のブリ」も美味しいんです。ほどよい脂の乗り具合が本来の味をたのしませてくれます。

(9/14入荷した北海道、日高のブリを塩焼き用に下ごしらえしたもの)
「鰹(かつお)」~スズキ目サバ科~
かつおは暖流の回遊魚で適度の水温を求め群れを成して移動します。黒潮と親潮が交錯する東北水域でたっぷりと餌を食べ、9月中旬になると南下を始めます。これを俗に「もどりがつお」といい、脂が乗っていて生食用として正に今がその旬と言えるでしょう。その成分はもともと高タンパクでビタミン類、DHA、EPAなども多く含まれ、とても栄養バランスのとれた魚ですが、この「もどりがつお」に関してはお肌のしわ、たるみに効くビタミンA(レチノール)が通常の4倍も含まれています。おいしくて健康によく美容にもいいこの魚、もう食べるっきゃない!


(気仙沼一本釣りのかつお) (たたきが旨い!!)
