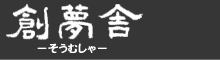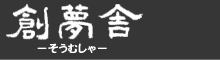東吾野の山中、ユガテというお盆を伏せたような平らな場所がある。春ともなると、2軒ある民家の周辺は、山桜の巨木や一面花でいっぱいになる。
ここから目と鼻の先に“ユガテの森づくり”をしている『西川木楽会』は、西川林業地の活性を願って、川上である山と川下である町の人々と飯能林業事務所とが一緒になって、94年に設立したボランティア団体です(2003年NPO取得)。
山主さんのご好意で30年間無料の使用協定を結んだこの場所に、97年の春より、杉・桧・サワラ・ケヤキ・コナラ・山栗・山桜・ホウなどを植林してきた。8年目を迎えた杉や桧も、これまでに下刈りを繰り返し、枝打ちをし、間伐をしながらも、家の柱や梁に使われるまでには5,60年の歳月を要す。160円程だった苗木を間伐材にまで育てても購入時と同額でしか売れない。山の荒廃を止められるのだろうか。山作業の一端にふれ、木のすばらしさとそれを生かした家のすばらしさを再認識。もっと、木を大切に使いたいと思う。次回からこうしたことの一端にふれてみたい。
|

 |
今は昔、江戸から見た西方に良質の材木を産する地があった。用材は筏で川を下り、「西の方の川から来る材」という意味から「西川材」と呼ばれ、江戸の町づくりに貢献してきた。江戸の初期よりの伝統を誇る西川林業は、古くから“関東の吉野林業”といわれ良質の用材を生産してきた。戦後の拡大造林から半世紀、国産材は毎年の成長量だけで、年間120万戸といわれる住宅を建てられるだけの量が山にある。ところが、木材需要の8割を輸入材に頼る現実。木を伐ったら植えることを繰り返すことが林業であるとしたら、その破綻は山を荒廃させ、自然環境や生活環境の破壊を意味しないだろうか。
今日の世界的な地球環境問題の意識への高まりは二酸化炭素を固定する森林の役割に注目し、無限の資源である木の活用をもとめている。たとえば、現在の25年ほどで壊されてしまう住宅を、少なくとも50年持つ木の家にすると産業廃棄物は激減するはずだ。生活の中にもっと西川材を使うことで、これまで日本の持っていた「木の文化」を見直す良い機会としたい。
|
大正13年に建てられたあさひ銀行飯能支店の前にある洋館風の建物は、織物協同組合として親しまれてきた。武蔵野鉄道(現在の西武鉄道)の事務所として使われたこともあった。当時、飯能から東京に向かって鉄道が敷かれたのだ。昭和初期の飯能駅周辺には14、5軒の材木商が軒を連ね、まさに“織物と西川材の町”であった。林業が最盛期の昭和40年ごろには飯能市内の製材所は40軒程あった。現在は8軒である。今、その面影を探すことは難しく、なんともさびしい限りである。
こうした中にあって、協同組合“西川フォレスト(プレカット工場)”の、木材の性質を科学し住まいづくりまでを視野に入れた取り組み、また、東吾野にある“木楽里”のように、裏山から伐採された西川材で誰でもが箸から家具までを楽しみながら作ることのできる工房のあり方などは、これからの木の活かし方のひとつとして注目したい。そして、自然の木を活かすためには、最先端の技術で取り組む姿勢と、職人たちのこれまで積みあげてきた、いわばローテクな技術を再評価することが大切と思う。
|
朝日新聞、7月6日の一面トップに「海の魚にもメス化現象」の記事。これまで海はその広さから、環境ホルモンによる魚への影響はないとされてきた。しかし、ダイオキシンはベトナム戦争で枯葉剤として使われ、後に奇形児などの社会問題化したことで有名。これらの人工化学物質は25mプールに数滴分で、私たちに大きな影響を与える。
新建材や家具に含まれる有機化合物(ホルムアルデヒドなど)は、新築病とも言われる「シックハウス」(アレルギー・めまい・頭痛・躁鬱など各自各様の症状)を引き起こす。この化学物質過敏症の発病の仕組みは、各自大きさの違う人体許容コップに、化学物質が徐々に貯まり、そこからこぼれた状態にたとえられる。一度発病すると、前に大丈夫だったものにも反応し、新しい家に住めない人もいる。だが、自然素材でつくられた木の家にとって、これは縁遠い世界。名栗村にある民宿西山荘・笑美亭(042-979-0164)は西川材を使い、木の香りする木組みの宿。この夏、シックハウスとは無縁な空間を体験してみるのも良い。
|
これからの家を考える手がかりとして、ご自分の家の柱や梁など、無垢の木を探してみると面白い。まず、外側を一周してから、各部屋を探索。梁は天井裏に隠れ、柱は和室に見えるぐらい。床・壁・天井・建具や枠類など木に見えて、実は張物やプリント物などの新建材。本物の木の少なさが見えてくる。木の家に住みたいと思いながら、新建材に包まれてしまった現代の家は、生活が便利になった反面失ったものも少なくない。今の家が健康被害や環境破壊の源になっていることを、以前この欄でお伝えした。
骨太の柱や梁が見えて触れた、かつての民家を、向井潤吉画伯は「民家こそが、人間と自然を結びつける、非常に重要な接点」と言われた。飯能にも茅葺の民家が僅かに残っている。架構や仕上げは木・土・草・石などの自然素材。これらは百年を越えて、なお現役である。ここには西川材のサイクルに適った、長持ちする木の家がある。次世代の子供達によい環境を手渡すために、自然と生活とが調和していた“民家の知恵”の生かされた住まいづくりを心掛けたい。
|
一昔前まで、家をつくるときには近くの大工さんに頼むのが当たり前であたった。隣近所の人々の暮らし方を理解し、木を中心に限られた自然素材によるの家の造り方を、大工さんが心得ていた。今日、生活は多様化し、多種多様な新建材や工法により、専門家でさえ戸惑うほど住み手の選択肢は拡がった。
家が欲しいと思ったとき“家は買うもの”と思い、住宅展示場に行く方も多い。そこであたかも新車を決めるがごとく、買う方、あきらめる方、疑問をもって帰る方など様々。
昨年、品質確保促進法で家の基礎、構造、雨漏りの10年間の瑕疵もついた。意地悪く見れば、一日でも期間を過ぎれば保障がないともとれる。しかし、住まいの本質は子供を育てやがて老いていく生活の場。生活の変化に有機的に対応しながら歴史を刻みつけられるものであって、住まいは買ったときが一番綺麗で時間ともに劣化し、手直しのできないものではいけない。そのために、住まい手と造り手とが顔の見える関係での家づくりが大切となる。
|
歳月を重ねて味わいを深めてきた民家には、人間と自然との暮らし方の知恵が詰まっている。日本の林業と民家の柱や梁の関係もその一つ。山の木は酸素を生み、二酸化炭素を年輪に刻み込んでいく。住まいにとって、木は湿度や熱や光や音の調節をするエコロジカルな無限の資源。木の香りや温もりに包まれた空間は潤いと活力に満ち、人に心地よい。同じ生命体の木に囲まれて生活することのすばらしいさが「木の家をつくることが暮らしを守り、森林を育てる」ことを実感させてくれる。
素木の会(73-8788)はこうした、人間と自然とが共生する住まいを実現させたいと思う方の出会いと学習の場。会では山の木が家となるまでの過程や自然素材・設計・施工の学習、建て方・完成の見学、建てた方との話会を通して、住まい手と造り手の顔の見える関係での家をつくりながら、“森林(やま)と都市(まち)を結ぶ住まいづくり”をめざす。さらに、百年住まい続けるために、住まい手同士や職人さん達とのヒューマン・ネットワークを視野に活動中。気軽に訪ねてみると良い。
|
林野庁では森林の評価額として、家の柱や梁などの建材やパルプの原料そしてキノコなどの林産物としての経済林で約4兆円、森林の持つ公益的機能、つまり二酸化炭素の固定、酸素の供給、水源の涵養、土砂の流出、レクリエーション機能といった環境林で約40兆円と算出。経済林より環境林に森林の価値を認めている。
日本の森林の蓄積量は、1年間の成長分でその年の全国の住宅をつくれるのに、木材需要の8割強が外国産材で、国産材は2割を割っている現状。こうした林業不振の原因の一つに、住宅の洋風化や工業化による、柱や梁の見えない大壁づくりが挙げられる。しかし、環境に対する関心は、民家や神社仏閣などの伝統的な木を生かした建築が極めてエコロジカルで、環境的負荷の少ない点に注目。これら建物は柱や梁などの構造材が見える真壁づくり。悪くなった箇所の交換が簡単で、維持管理や増改築がしやすく長持ちするつくり方の手本。つまり、持続可能な林業を育てることと私たちの暮らしを守ることは百年持つ木造住宅をつくることで手を結ぶと思いませんか。
|
朝日新聞【2001.11.26】のくらし欄「木の家に住む」で、輸入材におされてさっぱり使われなくなった国産材の木で家をつくる運動として“素木の会”が紹介された。西川材を使い地元の職人さんによってつくられた、美杉台の櫛部さんと唐竹の本橋さんの家づくりの経緯や、会のメンバーである山の井上さん、製材の大河原さん、大工の清水さんらの仕事を通して、国産材の家づくりが森をよみがえらせるという。こうした動きの全国組織として「緑の列島ネットワーク」の発足を伝えている。
素木の会では、次の5原則≪①地球環境を考慮した住まいづくり。②生活者の視点にたつ住まいづくり。③百年持つ木を生かした住まいづくり。④伝統技術を伝える住まいづくり。⑤町並みを考えた住まいづくり。≫を基本に木の家をつくっている。また、建て主(住まい手のプロ)と設計者(住まいを考えるプロ)と施工者(住まいを造るプロ)とが自立した関係で家をつくることが、いい家をつくる必要条件と考えている。家を建てた方々が連携し合い、木の家のすばらしさを次の世代に伝えることが出来たらと思う。
|
今、まちづくりのアクションプランとして、市民と行政と一緒になったまちづくりの活動が市内のあちこちで行なわれている。その一つ、サイン部会では飯能駅を降りた観光客を商店街に呼ぼうと、飯能駅と飯能河原を結ぶ道案内のサインづくりに取り組み中。相談を受け提案したのは、大黒柱をイメージした6本の道標(銀座通りと八坂神社の入口)と、江戸時代の高札をイメージした案内板(高麗横丁の入口)。材料は地元の西川材を使い、飯能の宝である山を身近な存在にしたいと思った。
限られた予算の中で、製材所の大河原さん、大工の清水さん、陶芸の佐々木さん、絵地図・金箔文字の吉田さん、飯能一小の生徒さん、それにサイン部会の方々で下準備が進む。3月10日(日)朝8時半、飯能商工会議所3階に集合の貴方によって実現する。小さいけれど、自分たちでつくる楽しさや地域への関りを身近に感じられる良い機会となればと思う。お昼は参加者で作り、青空の下で食べたい。参加費は無料です。ものづくりの楽しさを体験してみませんか。問合せ先:972-4040(吉田呉服店)
|
飯能を紹介する時、お気に入りの場所の一つとして、入間市の桜山の展望台からの眺めを推薦したい。子どもの頃、天覧山に登り、遠くに見える東京に憧れを覚えたものだ。その東京に背を向け、奥武蔵連山と手前の加治丘陵に囲まれた緑の中の美しい飯能を見ることができるから。まるで、グローブの指が山間部で、その谷間が入間川や高麗川や成木川、手のひらが平地部。そんな自然のグローブに囲まれ市街地を水晶玉にたとえると、削り取られた山肌や杉・桧だけの山、緑や憩える場の少ない市街地がそこに映し出されるより、四季の変化に富む山々や、緑と人々の活気に満ち市街地を見たいものだ。
扇状地に位置する飯能は自然と人間とが共生しやすい条件に恵まれている。7割の森林と3割の都市とがお互いに呼応し合うまちづくりは、森林の持つ多様な潜在力と市街地の歴史・利便性を互いに活用し合うことが大切。“自然の緑に囲まれた輝きのある都市”としてイメージできたとき、他の町には真似することのできない“飯能らしさ”のある町として誇れるのではないだろうか。
|
今年もスギ花粉に苦しめられた方も多いのでは。年々その被害が大きくなっている。山の手入れ不足、車の排気ガス、現代生活の歪みが過敏な人に現れていると言える。飯能市の市木に指定されている“杉”は日本の固有種で、「すぐ木」、つまり「まっすぐな木」に由来。桧と共に有用樹種として「木の文化」を支えてきた。しかし、山主自らお金を出さないと杉の木が伐り出せないような今日の状況は、西川林業の再生を阻むばかりか、私たちの生活に及ぼす影響も計り知れないものがある。
私は好んで、住まいの設計に杉の無垢材を採用する。人間の五感にフィットする素材との思いから。たとえば、厚手の杉の床板に素足で触れたとき、感じる心地よい感触。また、杉の柱・梁や壁で出来た室内のぬくもり感。健康で気持ちよい生活をするために、木の良さを知り、地元の西川材を暮らしの中にもっと使うようになれば、山の木を切り出すことができる。二酸化炭素を固定している木を大切に活用することで、地球環境に役立っていると意識することが大切な時代なのだから。
|
地元の山の木を使い、地元の職人達が建て、その“木の家”で暮らす。かつて、当たり前に行なわれていた事ができなくなって久しい。今、こうした住いづくりへの挑戦が名栗で始められた。戦後生まれの地元の人が中心となって、これまでに5回の公開の勉強会や見学会を行う。名栗の木を使った“木の家”づくりを目指して山主、製材所、大工、役所の人、それに設計者でつくる「名栗の木の家に住む会」だ。樹齢70年の木、10軒分を去年の秋に伐採。この春、山から運び出し、製材を待つ。
現在、千葉県の方を初め、村外の5家族が名栗村に住みたいと名乗りをあげ、住み手グループの結成目前。住まい手は山の木が家になるまでの仕組み、明瞭なコストを通して実質的な家が手に入り、造り手は森林の再生と村づくりができる。こうした住まい手と造り手の顔の見える関係での住いづくりは、この地域の林業の再生に、地域づくりの視点の大切さを教えてくれている。是非成功して欲しいと思う。詳しくは http://www3.gateway.ne.jp/~wrb/nagurinoki/ にアクセスを。
|
「地球人の世紀へ」と題して、朝日新聞の社説で、96年1月から99年4月の間に62本を掲載。その最終回、文明転換のために5つの提言をしている。その最初に、エネルギーを消費する金属・化学物質依存から、二酸化炭素を蓄えた植物を持続的に利用するために、「100年持つ木造住宅を建てよう」とある。かつて、100年持つことは当たり前であった民家。25,6年で壊されゴミとなる今の家は生活の器から商売の手段となり、山の再生はおろか生活を脅かすまでになってしまった。
この6月より施行されたリサイクル法で、環境負荷の大きい材料の使用制限や家の解体費用の急騰により、家は壊す時のことを考えてつくる時代となるだろう。京都議定書で二酸化炭素の削減は6%のうち3.9%を森林が担う。そこから生産される材木は人手を加えないほど自然と土に戻る環境的な優良素材。つまり、樹齢6,70年の木を使い家を建てたら、それ以上の長持ちする“木の家”をつくることが、持続可能な社会づくりの道理。100年持つ木造住宅を誰もがつくれる仕組みがほしい。
|
中央線沿線、荻窪や中野の辺り、繁華街から少し離れると静かな住宅地がある。新建材でつくられたそんな無機的なまち並みのなかに、昔の板壁や土壁の家、そして路地やそこにある緑を見つけるとホッとする。
そんな住宅地の一角に住むKさんは築48年の家の建て替えを決断。金物に頼らず、伝統的な仕口・継手による木の家の設計も終わり、さあ建てようという段に、頼りにしていた町内の棟梁が身体を悪くされる。彼の一番弟子に話したところ、図面を見て、できないとの事。その後、紹介された別の大工さんも今の仕事が忙しいと、知人の大工さんを連れて私の事務所に見えた。これまでに設計した住宅を見たりしながら、「こうした木の家はいいね。若い頃を思い出すよ」と、懐かしむ様子。仕事をしたいが即答をせずに別れた。翌日、「今回の木を生かした仕事はありがたいが、都内では刻む作業場も狭くできない」と、あきらめの電話が入る。プレファブやプレカットが広まるなかで、日本の“木の文化”の担い手であった匠の技術を次の世代へ継承する難しさを実感した。
|
明治の文明開化は江戸の文化を切り捨て、その後の日本は西欧化を国是としてきた。建築の分野では大工の技に変わって、西欧のテクノロジーによる大学教育が行われた。戦後の復興と高度経済成長そしてバブル経済は過去の建築的遺産を壊し、日本の“木の文化”は社寺を中心とした文化財や一部の住宅でその“匠の技”を細々と今日に伝えている。
石油文明の落とし子である新建材がシックハウス症候群や化学物質過敏症の原因であることや、大壁工法が建物の寿命を短くしていることが解かるにつれて、伝統的真壁工法が見直され始めている。構造設計家・増田一真氏による新伝統工法セミナー(1年間12回)もそのひとつ。全国に先がけて、6月19日に小川町で県内外の設計者、施工者など80名程の受講者に行われた。今の家と昔の家の違いを学ぶ中で、伝統的工法の再興がこれからの持続可能な社会づくりの基本であると唱えていることに同感。こうしたセミナーに参加する若い大工さん達に“木の文化”の灯火を託したい。
|
自宅を“木の家”でつくられた小山市の保育園の園長さんが、自らの経験を生かして無垢の木の保育園づくりに取り組んでいる。市が土地を提供し、民間が保育園を建てる方式の設計コンペが昨年行われた。私達の提案した、「地元の職人が国産材を使い伝統的工法でつくる」260坪の保育園が選ばれ、来春の開園に向けて工事が進んでいる。
建物の外壁は杉板と漆喰壁で、内部は2間グリッドに林立した6寸角の柱の頭上を梁が繋ぎ、床を38mmの厚さの桧と杉、壁を杉板と漆喰でつくり、天井を杉板と鉄板波板と吸音板とで屋根の勾配なりに張り上げている。かつて、木造校舎で過ごした原風景を“木の保育園”は目指している。それは、無垢の木の温もりや香りのある空間のすばらしさを子ども達に味わって欲しいとの思いからだ。今、5組の大工さん達が柱や梁に刻んでいる仕口・継手を見ていると、まさに“木の文化”として技を見る思いがする。建て方は10月8日から23日に行われる予定。
一般公開を計画していますので、建て方を見学したい方は創夢舎にお問い合わせください。
|
次世代の子ども達によい環境を残すために、省エネルギーと環境に配慮した生活が求められる。そのためには目先の省エネでなく、生産、使用、廃棄までの「モノの生涯」にわたってエネルギーと環境負荷を数値化し検討(ライフサイクルアセスメント)する必要がある。車が2万とすると、家は10倍の20万の「モノ」で組み建てられる。
現在の家には多くの新建材が使われ、その生涯数値は莫大となる。たとえば、アルミサッシの窓は同じ木製の窓をつくるときの140倍のエネルギーが要る。しかも、空気中の二酸化炭素を炭素の形で自分の体に貯えている木には、炭素がその重さの半分あるのに、アルミにはない。木は朽ちて土に返るが、建築廃材には環境汚染の原因となるものも多い。木は伐ったら植える繰り返しのなかで、大切に使えば無限の資源となる。また、木は人間に一番近い、エコロジカルな素材、住み手にとってシックハウスなど無縁な健康的な住まいを提供してくれる。こうしたところに、木の家をつくる意義がある。
|
私は設計する時、建て主の条件に加えて、①自然があること、②歴史や風土があること、③安全性があること、④コミュニティーがあること、⑤美しさがあることを心がけている。一つひとつに思い巡らすことで、住まい手の家や地域における “らしさ”を創れたらと考えてのこと。これら5項目のフィルターを通すことで、ものを創造したり、検証したりすることができる。これを“ウッディーめがね”と称して愛用している。
使い方で、意外と普段気が付かない身近な“吾が町再発見”もできる。例えばこの眼鏡で、今ごろ紅葉の美しい観音寺から諏訪神社にかけての県道沿いを覗くと、①と②と⑤は在るが、③と④が欠けているのが見える。そこで、車道と分離した歩道で車椅子も通れるようにし、飯能河原を見下ろせる辺りに西川材のウッドデッキを設けると、自然と立ち止まり話も弾む。一段と飯能らしい“緑のトンネル”となるといった按配。皆さんも試してみてはいかがですか。
|
子供の頃、父に連れられて天覧山わきの水道山に松飾りの松と榊を取りに行った。しめ縄は祖父が作り、一夜飾りとならぬよう、暮れの30日までにお正月を迎える準備を家族みんなでしたものだ。松飾りに一年の幸をもたらす年神さまが降りると信じていた頃、家の中のいろんな場所に、さまざまな神さまが存在していた。台所には恵比寿さま、井戸に水神さま、厠(かわや=トイレ)には厠神さまというように・・・。住まいが生活に欠かすことのできない、大切な場所であった。
昨今の世相に目を向けると心の痛むことばかりが目につく。社会に物があふれ、生活が豊かになるにつれて、人間として大切な何かを見失ったと思える。人間はひとりでは生きていけない。神さまは、家族のコミュニケーションと自然に対し畏敬の念と感謝の気持ちを持つことの大切さを、松飾りに託していた気がする。もう一度、里山に入り草木の匂い、梢を渡る風の音、野鳥のさえずりといった自然の営みに五感で接してみよう。新しい年、人間と自然との関わりを考えるきっかけとしたい。
|
工業の機械化はより安くて便利なモノや快適な生活を私達にもたらした。が、自然の再生力を超える大量生産・大量消費が地球温暖化を生み出したことで、二酸化炭素を吸収する森林が注目されている。また、最近の産業へのロボットの進出などによる労働の質的変化が、今後の私達に、生きることや働くことの意義を考えさせている。
戦後の山(林業)を経済林ととらえてきたことが、山の荒廃と山村の衰退につながっていると思う。“人間は自然から離れては生きられない”ことを、かつて山(自然)と共生したエコロジーな暮らしは物語っていないだろうか。長期的なビジョンと環境的視点に立った地場産業が地域らしさと個人の存在感を生む原動力と考える。そこで、地域の多種多様な人達から人間と自然が共生できる知恵や知識を学び、山(森林)の自然環境や西川材を地域づくりに生かし、山(文化)を育て、都市から山村に人を呼戻し、心豊に暮らせる場づくりの実践として“山の学校”を提案したい。
|
ベーゴマやコマを回す。外遊びに興じた子供時代を過ごした私達の世代からすると、コマに紐を巻くことのできない今の子供たちを見るともどかしい。今も、コマは世界中にある玩具。10数年前に江戸独楽職人の広井兄弟との出会いなどをきっかけに、自由の森学園の塗矢先生を中心に“コマ回し大会”を始めた。昨年は飯能駅のペペホールで、今年は3月30日(日)に“第11回県知事杯争奪コマ回し大会”を銀座通りのイベント広場で行う。午前中にコマ教室もあるので親子で参加ください。
昔の子供遊びと思われがちな独楽は、その歴史も古く多種多様な形や遊び方が各地に残る。また、鋳物のまち川口近くで毎年行われベーゴマ大会は地域に根付いてきたと聞く。飯能でも高麗横丁や路地裏のある商店街で、独楽は魅力づくりの“コマ”になると思う。昨年12月19日、NHK“いっと6けん”で吾野の独楽の館が放映された。当館では日本独楽の会会長の八木田コレクションや世界の独楽を展示。毎月第一日曜日の午後開館しているので是非見学を。連絡先090‐3214‐4013(大河原)。
|
埼玉県では農林部が中心となり、県民の家づくりに県産材を活用してもらおうと『100年の家づくりプラン』の冊子を発行します。生産可能で二酸化炭素を貯蔵する県産材の杉・桧で家をつくることは、循環型社会の構築や地球温暖化の防止や地域経済に貢献すること。また、木の樹齢以上長持ちする家づくりは森林を育てると共に生活環境を守ってくれる。こうした考えに基づき、一年間かけて、建築設計事務所、大工・工務店、製材工場や森林組合など24人が協力して、12プランを提案した。
内容は、「100年の家をつくる」ことの意義と5つのポイントの説明に始まり、具体案として12プランを掲載している。それぞれのプランは建築概要・平面や矩計図・予算・設計者のコメントなどと共にカラー写真入で見やすい。木材の使用量と費用や巻末の木材に関する資料もあり、これから家を建てようと考えている方には参考となると思う。
問合せ先/埼玉県農林部林務課 県産木材促進担当(高野・丸山)電話:048-830-4321
|
福島県以南から南にかけ九州の屋久島まで広く分布している桧は、杉に次いで多く造林されている日本を代表する常緑針葉樹。天然林の木曾桧は青森ヒバと秋田杉とで日本三大美林として知られている。昔から桧の家は高価なものとされ、今でも神社仏閣や高級建築物に桧造りが多い。桧の高級材としての価値は育成期間の長さから来る希少価値や年輪の美しさ、独特な香りや高貴な色合い、耐久性や加工性の良さなどにある。
普段着の生活感のある空間をつくるために西川杉を設計に採用することが多い中で、東岩槻に建築中の“木の家”で西川桧の柱や梁を使ってみると、背筋の伸びた透明感のある空間を感じる。面白いもので、桧と杉の床板にそれぞれ両足を乗せておくと桧は冷たく、杉は暖かい。冬にスリッパを必要とするか否かほどの違いがある。桧は腐れには強く、建物の土台や浴室など水場回りによく使う。つまり、木は適材適所に大切に使うことで生きてくる。
|
この欄の⑮で紹介した“西荻窪の家”が完成した。大工さんを探すこと5組目、限られた予算の中でその大工さんは「父の時代までは当たり前だったが、最近珍しいよ。金物を使わず伝統的な仕口・継手で建てるのは!」と快諾し、心を込めて建ててくれた。やがて出来上がるに連れ、足繁く現場に通うのが楽しみとなった建主は、大工さんの手仕事のあちこちを指差しながら「無垢の木っていいね」と口元をほころばせながら私に話された。木の家が持てる喜びを感じていることが嬉しかった。
普段、素木の会(⑦と⑨で記載)の会員を中心に完成した “木の家”の見学会をしている。今回は時間が無くあきらめていたら、建主より「うちは見学しないの、大工さんの仕事を是非知ってもらいたいのに!」の一言に、引越し前日の見学会を催す。当日の参加の関心は大工さんの技と木の家の良さに集中した。引越し間もなく、建主から「今度の家は新築なのにずっと前から住んでいるような感じで、気持ち良い。ありがとう」の一報をいただき、大工さんの“匠の心”のお陰と感謝している。
|
住宅の床を始めとして、屋根の野地板から家具まで、西川材の杉の厚板を設計に採用して10年以上になる。厚さ38ミリ、巾180ミリの杉板は飛び跳ねても、ピアノをどこに置いても大丈夫なほど頼もしい。新建材のフローリングに比べ、リーズナブルでエコロジカルな健康素材だ。塗装をしない無垢の床板は断熱と保温効果で、冬でも素足で過ごせるほどのスグレモノ。また、時が経つほどに光沢を増し、味わい深くなることも楽しみの一つと言える。
床板の日頃の手入れは水拭きが基本。冬場は水の滴るぐらいに、夏場は固めに絞って拭くことで室内の湿度調整もしてくれる。梅雨の今頃は室内がサラッとして、蒸し暑い夏は床板に寝転ぶとヒヤッとして、気持ち良いのも杉の厚板の特徴。こうした西川材の杉を家づくりに大切に使うことで、地元の森づくりや大気中の二酸化炭素の削減にささやかだが役立っていることも嬉しい。住まい手の健康に良い自然素材として杉の厚板をこれからの住まいづくりに取り入れてみてはいかがですか。
|
戦後、人々が山村から都会へ流出したことで、林業の荒廃を招いた。しかし、最近の世界的な環境への関心から、各地で、都市住民が森づくりに参加し始めている。この辺りでも、西川木楽会がこの11月のNPO法人取得に向けて動きを始めた。当会は川上と川下の市民と行政との参加で、1994年に発足し今年で10年目を迎える。朝日新聞に紹介された第1回の総会以来、東吾野のユガテの森づくりを始め、木工や各種イベントの開催と参加や広報誌づくりなど、多彩な活動をしてきた。
今日の山にはかつての“森林文化”が欠けていると思う。山の価値は杉と桧だけでなく、その多様性にこそある。私たちは今の便利さだけの生活に浸る余り、“人間は自然の一部である”ことを忘れた感がある。もう一度、地に足の着いた暮らしをするために、「木の文化の再創造」「地域で生きる場づくり」「森林(自然)と都市(人間)
を結びつける住まいづくり」を念頭に、西川地域で生活できる“場”の模索を提案したい。西川木楽会への問合せ先は042‐978‐1947<マチ>まで。
|
飯能河原の優れた自然環境を守り、子ども達が安心して水と遊び、訪れた人々にとっていつまでも心に残る景勝地として、これを後世に引き継ぐため、飯能地区まちづくり推進委員会が「自動車の乗り入れはしない」「石の上で直に火を燃やさない」「ゴミ、残り火等を放置しない」「鉄板等を川で洗わない」「花火は、夜9時以降やらない」の5つの指針を決め、市の50周年記念事業の一つとして、8月7日、飯能河原に市民や大工さんなど関係者50名以上のボランティアの手で看板を立てた。
飯能河原の入口の土手に立つ,指針が金箔文字で書かれた西川材の桧柱と、他の杉柱など24本が飯能河原や西川材への関心の糸口になればと期待したい。手づくりによる多少の不安を残しながらも、周辺の環境整備を市当局へ働きかけたいとの意見のあったことは、今後の維持管理に光明と思う。そして、柱の木口の保護をかねて、陶芸家の佐々木さんの“川原の自然”をモチーフにした陶板がその頭に載って完成する。30日の朝9時ごろを予定。関心のある方は是非ご参加ください。
|
吾野中学校では、地域の人々のとの交流を通して、身近な文化・芸能などに触れる「体験講座」を毎年行っている。今年は9月6日、例年人気のあるうどんやこんにゃくづくりとその試食。楽しみながら挑戦した創作凧・枝笛・コマづくり。数時間の練習で驚くほど上達を披露して見せた大正琴・盆踊り・祭囃子など11の講座を通して、生徒・講師・先生ともども新鮮な体験となる。
周囲を山に囲まれた西川材の中心地にある中学校は、かつての高麗郡の西端。高句麗からの渡来人と一緒に持ち込まれたコマは、高麗の名と関係がありそうに思う。大昔から今日まで世界中にあるコマ。日本には世界でも類を見ない芸術的発展をした江戸独楽がある。今回は北朝鮮からロシアで親しまれているムチゴマをつくった。ワイン瓶ほどの丸太から湯のみ茶碗の底を尖らせた形のコマをつくり、枝に布を結びつけたムチでたたいて回す。体育館での発表会には、教頭先生や飛び入りも加わりエキサイティングに皆も回った。杉や桧でもつくれるので、地域おこしの一つの駒になれればと思う。
|
飯能地域で生産された材木は、その昔「江戸から見て、西の方の川から来る材」から「西川材」の名で知られ、江戸の町づくりに貢献した。材木は筏に組まれ、下流に行くに従い組み足され、最終段階では幅4間、長さ20間程の筏〔壱艘〕となり、筏師が1週間程かけて千住に流送した。大正4年に開通した武蔵野鉄道(現・西武鉄道)により、大正末期には筏流しは途絶えた。
今年9月7日、駿河大学の大久保先生を中心に、筏流しが原市場から阿須まで丸一日かけて再現された。車で運べば30分で10倍程の搬送も、数十本の丸太を筏に組み一日掛かり。打ち上げに参加した人々は来年も是非やりたいという。現代の私達が忘れてしまった時間の流れも体験した様子。今回の筏は老若男女、多様な人々を乗せて、“森林の文化”を山間部から都市部に発信してくれているのだと思う。平成17年元旦には名栗と飯能が合併する。森林の持つ文化とその多様な価値を生かせる地域となってほしい。
|
樹は私たちと同じ生物。飯能市上直竹タブノキや越生町上谷の大クスノキなどの巨木を見ると、まさに神が宿っていると感じる。そもそも、地球上で樹は一番長生きの生物。7200年も生きている縄文杉を筆頭に、各地の巨木は、過酷な自然の中で自らをその幹で支え、その地域を樹齢と同じだけ見続けて来た。5,60年以上の樹から取れた柱・梁を使って、かつて民家は百年と住み続けた。樹はその寿命以上の使われ方をしないとバチが当たると思う。
今の家は、コストを切り詰め、人手を省き、木を切り刻み加工し新建材で、建てることが主流。木は手を加えるほど自然から離れ、多くの木の特色を失っていく。新建材は寿命が短く産廃ゴミとなる。しかし、木はやがて土となる。「柱は木が主」と書く。その木は同じ重さで比べるとコンクリートや鉄よりも強い。木は無垢のまま使ってこそ、その良さを生かせる。
“無垢の木で家を建てる”ことが森林の恵みである木材を生かす道理ではないだろうか。
|
春の市街地を囲む山肌が一面に萌黄色に沸き立つ。上空から名栗方面を見ると、杉桧の黒木と落葉樹のパッチワーク模様の山並みが連なる。ここに住む人々は、森林の多様な素材や環境を活かした農林業、木工、染色、陶芸、絵画、文筆、民宿、飲食店、福祉などの多彩な仕事で生計を立てている。地元の棟梁が西川材でつくる“木の家”に住み、森の生産品や有機野菜に個人が直に値段をつけ、産直市場で売って現金収入を得る。山の生活は自然の中での子育てをしたい若年層にも受けている。
一方、市街地には高木が点在し、建物はその高さを超えないように規制されている。鳥のさえずりや町の匂いを取り戻すのに、電気自動車の普及や路地や井戸端などの復活が一役買っている。路地裏にはシニア層も多く、巣鴨のとげぬき地蔵並みの賑わいだ。そこには西川材でつくられた、玩具や環境や健康にやさしい様々な品物が展示・即売する店がある。情報通信の浸透は、山と町、個人と世界を結ぶと共に、足が地についた生活を可能にしている。そんな“はんのう”の初夢を見た。
|
暖房が恋しいこの季節。昨今の暖房の熱源は、石油・電気・ガスが一般的だ。が、これまでに10数軒の薪ストーブのある住宅の設計を通して、ゆれる炎を間近に見ながら家族団欒の場ができたと思う。お父さんの帰りが早くなったと喜ばれたこともあった。薪ストーブには同じ薪を使う暖炉と違い、暖房効率の良さや煤の排出が少ないことなどの長所がある。冬支度の薪の調達や薪割りの苦労も、オーロラのような炎を見ると報われると、虜になる建て主も多い。
歴史のあるヨーロッパ製のものは、ステンレスの二重煙突で、ストーブ本体価格の倍もするが優れている。薪は針葉樹より広葉樹が適し、香りの良さで桜が喜ばれる。調達は仲間同士や造園業者と知り合えば運搬賃程度で手に入る。ダイオキシンなど有害物質も出さず、石油に頼らない薪ストーブは、間伐材や焼却木材を活用することにより地球環境にも貢献できる。埼玉県では木材ペレットを燃やすストーブを開発し、商品化した。寒い冬、薪ストーブの研究してみてはいかがですか。
|
友人のキーホルダーは桧の枝を輪切りにして自分で作ったもの。5年以上は使い込んだと思われるそれは、無垢の木なのに漆塗りような光沢と味わいがある。名栗の木工家による透かし彫りの名札をサビアの郵便局の窓口で見つけた。飯能市長室の壁に西川材が使われていた。気にかけて身の回りを観ると、名刺・名札・コースター・お椀・植木鉢・紙巻器・便座・額縁・店の看板・椅子・テーブル・戸棚など無垢の木が使われていることに気づく。そして、無垢の木の家はその際たるもの。木が見直される時代になりつつあると感じる。
無垢の木は土にもどる。生活の中にもっと木を使うことで、暮らしの潤いと西川材の活用につながる。均一な商品を大量生産・大量消費するのでなく、多彩な生活を地元の産業で支える仕組みづくりがこれからの地域づくりのポイントと考える。山はそんな素材を供給してくれる宝庫。百年先の西川地域をどうするかということは、今回の飯能と名栗の合併でも大切な視点と思う。
|
設計の仕事は基本設計と実施設計、そして工事監理でワンセット。建て主の意向を受けて、具体的な家のイメージを建て主と設計者が共有するまでを基本設計。この期間は両者にとってエキサイティングで創造的な時だ。次の実施設計は、施工者が見積りとその後の工事をするための詳細な図面をつくることで、施工者とのコミュニケーションの道具づくりとなる。ここまでに最低半年、数年に及ぶことも珍しくない。設計料は同じなのだから、建てる方は充分な納得と設計者との信頼を築く期間としてほしい。工事監理は、施工者の見積り査定・工事契約の仲立ちをし、図面どおりの建物を引き渡すまでの期間。ここでは現場の打合せや材料の確認、建て主の変更とその査定などを行う。
引き渡された“木の家”は完成ではなく、その家族の生活とともに生きていく。生活の変化とともに維持管理をしながら住まうことが必要となる。こうした一連の過程をサポートすることも設計者の役割としてある。そのために、中立の立場で建て主と施工者の架け橋でありたいと思う。
|
全国から100名を越える賛同者が池袋の芸術劇場に集まり、1年後のNPO取得に向けて、“伝統木構造の会”の準備会が発足した。この会は増田先生(16で記載)を中心に、今日の持続可能な社会づくりに欠くことのできない、戦前まで日本の建築文化の中心をなしてきた伝統木構造を我々の代で滅ぼしてはいけないという願いが運動の原点にある。その為に、職人と設計者と山元とが中心となり、多方面の支持を得て、よい住まいとまちづくりをすすめる大規模な運動展開をアピールした。
現代木造は、伝統木構造を改良したものと多くの人々は信じているが、伝統型と公庫型とは、共通点を持たない正反対の性格の木構法と先生は言う。伝統木造が法規制で締め出されたため、若い大工たちは造りたくともその現場がなく、老大工からその木組みを教わる機会がほとんどない。平成12年の法改正により限界耐力という手法で、伝統木構造の家を造れる道筋が出来た。家をつくろうとする際、世界に誇れる建築文化である伝統木構造を次の世代につなげる絶好の機会として取り組みたい。
|
最近の浴室はユニットで、暖房・乾燥機付き換気扇、多機能シャワー、ジェットバスや自動お湯張りと機械仕掛けで、身体を洗濯する感じ。掃除が簡単で清潔というイメージがコマーシャルされ、施工が簡単で利幅が多くクレームが少なく便利さが受けている。私の子供の頃、風呂場は薪で焚くので壁や天井は煤で真っ黒だった。今でも覚えている、裸電球の光を受けて、湯気が天井から落ちる時、まるでダイヤモンドのよ風呂場うに美しかったのを。裸で過ごす風呂場はもっと安らぎがあってよいと思う。
私は壁や天井に西川桧や青森ヒバを使う。換気をよくすればカビをそれほど心配することもない。タイルと違い壁に水滴のつくこともなく、冬の寒さも和らぐというものだ。浴槽も鋳物ホーロー並みの価格で高野槙や桧のものが手に入る。また、浴室用のコルクタイルを使えば、オール木造りの風呂場も可能だ。人造大理石の浴槽や樹脂系の内装に比べこうした風呂場は大変エコロジーであり、エコノミーでもある。木の香りや、木目を見ながらの入浴はホッとするひと時である。
|
ガラガラッと格子戸を開けて、出入りする玄関が懐かしい。住まいの顔といわれる玄関には、その家の品格・家柄・風格が表れる。その役割は、家族の出迎え、来客の応対、宅配・郵便・新聞など物や情報の出入り口。時にはペットも出入りする。その為、公道から玄関までのアプローチの形状、ドアの形式、床の段差や視線の高さをどうするか。また、玄関と各部屋とのつながり、玄関の方位や位置によっては、他の部屋の採光や通風をどう確保するかが設計の勘所。また、下足入、コートからゴルフ・釣り・スキーなど趣味道具の収納、手摺、花台、腰掛、敷台など考えることが意外とある。
今は夢物語か、隣近所の人が自由に出入りできる玄関は。防犯上、二重、三重の鍵を掛けたドアも珍しくなく、人を拒むようで寂しい気にさせられる。アルミのドアはその冷たさを助長している。玄関前に立った時、木の香りや、手掛けの肌触りの良さや、見た目の親近感を与えてくれる木製の建具にするだけでも、人にやさしい住まいの顔となるのではないだろうか。
|
日和田山を望む横手台団地に、金物に頼らない伝統構法の真壁の家が建ち始めた。建て方はゆっくりと丁寧に柱と梁が組み込まれ2週間日を要した。“みんなで組み上げるぞ”という一体感が職人の掛け声に表れる。一本の柱が建ち、最後の棟が上げるまで経過とその仕事振りとを見ていると、大工さん達に自然と感謝したくなる。その上棟式では、住み手と職人と設計者がこの家のことで話が弾んだ。こうした一連のプロセスを体験すると、“家は買うのでなく造る”ということに納得がいく。
展示場で選び、買うプレファブ住宅は外壁から屋根まで一日、2ヶ月あれば完成する昨今。一見、非効率、非経済的に見える伝統構法の“木の家”だが、最終的には大手プレファブと違わないコストで建ち、百年の長持ちと住まい手の暮らしを豊かにする術を持っている。エコノミカルでありエコロジカルである伝統の大工技術は文化だと思う。この猛暑の中、大工さんから「遣り甲斐のある仕事だ」と言われたことが嬉しい。
|
子供室って何?乳児期は母親の傍で一日を過ごす子供も、少年期に自立し、思春期を経て、やがて家から巣立つ。子供の居場所は成長と共に、親の周辺から兄弟一緒の部屋、やがて家具や壁で仕切られた個室へと変化する。子供が独立すると、納戸・家事室・書斎・空き室や来客の寝室など多様な使い方ができる。そして、設計する上では、「こんな家族を築きたい、こんな人間に育ってほしい」と話し合いながら、広さ・形・配置など既成概念にとらわれない子供室を考えることが大切と思う。
例えば、机・本棚・ベッドなどは子供用の新建材の既製品より、無垢の木でフレキシブルな空間を大工さんに造ってもらうこともできる。プライバシーとばかりに鍵付きドアの個室より、鍵なし引き戸で入室時の声掛けや家族の気配が感じられるコミュニケーションのとりやすい空間が良い。また、子供室より、家族団らんの場を広くすることで、孤立感と不安感のない家族関係を築く工夫もできる。住まいは親がつくり、子供はその住まいによってつくられるところがあると思いませんか。
|
家の基礎工事にかかる前、その土地の神を祀って工事の安全を祈願する地鎮祭。近年まで、神に祈ることで、台風や地震などの自然災害から家と家族を守り、家内の安全な生活ができると信じてきた。矢颪の神主の滝沢さんは「核家族の進んだことと地鎮祭の少なくなたことは関係が深い。」と。また、最近の物騒な世相を憂い、「太陽があることで草木が育ち,風があることで四季を感じ、空気があることで生きている。人間は自然の一部であること。また、私たちが生きていることは両親がいて、祖父母がいて、その先祖がいるということを理解し、家族の絆を取り戻してほしい。」と話された。
|
 |
 |
神主さんの祝詞に耳を傾けていると、普段見過ごしがちな雲の流れ、辺りの何気ない音や香りを感じるとともに、不思議と神聖な気持ちになる。着工時に、こうした場を住まい手とつくり手が共有し合うことで、“これから一緒に協力し合って木の家をつくろう。”とする意識が生まれる。こうした節目の一つの行事と知ると、地鎮祭が有意義なことに見えてくるのではないだろうか。
|
|
国道299号線の(俗称)吾野バイパスが開通して6年が経つ。秩父方面に向かう通過交通が激減し、これまで出来なかった街道の真ん中を歩いてみると、出桁造りの町並みや道に面した庭先と空の広がりの新鮮さに改めて驚かされた。かつて秩父街道の宿場町として栄え、近在の人々で賑わったころの町並みを思い描きながら秋の一日を散策してみると、新しい吾野宿が見えてくると思う。
11月14日の県民の日、ここ吾野宿で第12回“コマ回し大会”が行われる。ベイゴマと木ゴマと西川材の間伐材で作ったムチゴマ“西川ゴマ”のコマ回しで、大人と子供の勝者は県知事賞と市長賞がもらえる。当日、自治会やボランティア団体では、コマ回し教室・西川材製品の展示販売・嘉手川美術館と独楽の館の無料開館・吾野宿食堂などを催すので、「吾野宿に集まろう」と呼びかけている。吾野駅やバイパスからのアクセスの工夫、ハイキングや山登りのルート開発、“道の駅”の誘致、街道沿いの朝市など出来そうなことから始めと、“吾野宿”らしさのある地域ができるのではないだろうか。
|
台所はその時代の食生活の位置づけや価値観が反映されるので、歴史的に一番激しく変化してきた空間だ。最近、レトルト食品や冷凍食品や外食が当たり前となり、家族で一緒より個々に食べるといった食事の傾向にあるようだ。また、設計もシステムキッチンを選べば台所は完成と思い勝ちだが、そのシステムキッチンの費用で、“木の家”の構造材のすべてを賄えることを知ってほしい。台所の設計は住まい手がどんな食材を、どう料理し、誰とどんな風に食べるかを話し合う事から始まる。
各家庭の食べ事は多彩で、夫婦二人の、二世帯に対応の、車椅子対応の、木づくりの、手づくりパンができる、ガスコンロは少し低めの、老夫婦の小さな、収納が多い、汚れにくい、風通しの良い台所など話は尽きない。設計も終盤になると、時の経過とともに使いやすい台所としたいとのことから、私の場合には大工さんがつくる個性的なキッチンの実例が多い。そして、豊かさのバロメータの一つである食べ事は、生活の基本が健康的な衣食住にあると気づくことから始まると思う。
|
山で大切に育てられた杉や桧を、真壁づくりの家は柱や梁の構造材として見せてくれる。かつて、山と家がリンクしていた頃の林業が柱梁林業と呼ばれた所以だ。現代住宅は柱梁を隠す大壁となり、見せるのは和室の柱くらいで、しかも無垢材より集成材が多い。昔は一本の木を無駄なく活用する文化があったのに、今は人手の入らない山に多く杉や桧が放置されている。伐っては植えることを繰り返す人工林は環境にやさしいのだから、人間と自然の適切な付き合い方が求められている。
西川木楽会(27で記載)会員の佐藤さんは柱梁や板などの木の縦使いから、輪切り使いによる木の横使いを提起する。木を梢から根元まで生かしたいとの思いを感じる。輪切りにされた木の太い根元はテーブル、植木鉢、腰掛。幹は小物入れ、箱、マウスパット。太い枝は鉛筆立て、コースター。細い枝は箸、鉛筆、ボールペン、ポインター、杖、帽子掛けなどを実作。アイデア次第で多種多様な商品ができる。間伐材の西川ゴマ(42で記載)もその一つ。元気な山を取り戻す手掛りの一つと思う。
|
バブルの時、解体される危機に遭遇した大通り商店街にある土蔵造りの店蔵(絹仁)が、飯能市に寄贈された。この店蔵の裏庭に、江戸時代の素朴な土蔵がもう1棟ある。共に貴重な文化遺産だ。この他にも明治・大正・昭和初期に建築された土蔵・洋館や、3階建て町屋などが市街地に残されている。川越市が購入した鏡山酒造の土蔵で、去る1月16日に「木の文化とまちの活性化フォーラム」が開催され、所沢の明治の商店や行田の足袋蔵の再生が報告された。
こうした歴史的建築物がクローズアップされる背景には、現代生活の中から失われていく歴史やコミュニティに対する危機意識と環境問題があると思う。地元で育った木材を使い、地元の職人がつくったこうした歴史的建築物は人間と自然との共生した“木の文化”
の再生とまちの活性化の要であり、自然と共生した住環境のありようと地域性を示唆してくれていると思う。そして、これからの“飯能らしい”まちづくりには市民の力の結集とほかの地域とのネットワークが大切と考える。
|
戸外で用を足していた太古から便所という部屋へと変遷してきたトイレ。トイレの不浄なイメージは汲み取りから水洗便所、和風から洋風便器になり消えつつある。トイレの内装は化粧合板やビニールクロスなど新建材が一般的だが、時にはプライベートな思案の場ともなるトイレなので、これまでの経験から杉や桧の無垢材や漆喰も使いたい。しかも、木の香りや温もりのある空間はトイレに適しているのではないだろうか。
設計する時に、洗面・浴室・寝室など他の部屋とトイレとのつながりが住み心地に影響してくるので、その位置や広さは重要だ。また、コストや使い勝手を左右するの設備(便器・換気扇・暖房・照明)は多種多様なので、自分なりの価値基準を持って選定したい。トイレに1坪の広さがあると、プラスアルファーを加えることができる。たとえば、本棚・隠し机・洗面台・郵便受けなどを設けることで、プライベートな楽しみがかなえられると思う。
|
シロアリは蟻でなくゴキブリの仲間。光を嫌うのでドラキュラのようだ。シロアリの姿を見る機会は少なく、春先に羽化した羽蟻を見ることでシロアリの被害に気付くことが多い。何を隠そう我が家でも10年程前、浴室に羽蟻が出て、改修した苦い経験がある。現代の大壁造りの家では土台や柱などが腐っても判らず、適切な維持管理が行われにくいため、大事に至るケースが多い。そこで、あらかじめ薬剤を土台や柱に注入したり、土壌に散布したりすることが一般的なシロアリ対策だ。
ところが、10年間保障されている防蟻剤は私たちの健康や環境を脅かし続けているといえる。本来、シロアリは倒木や木材を土に戻す生物として大切な役割を担っている。我が家の浴室を改修した際、土台と一部の柱が土と鉄筋状の木の芯に変わっていたのに驚かされた。シロアリは水気のある木を好んで食べるが生きた樹は食べない。シロアリを寄せ付けない家は通気性を良くし、木材を乾燥した状態にさせておくことで薬剤を使わずとも可能だ。その点では現代住宅より、民家に軍配があると思う。
|
町を歩いているとき、視線の止まる建物や風景がある。歩道の突き当たりにある建物や街中の塔や巨樹などで、これをアイストップという。町だけでなく家にも、床の間やニッチ、窓からの眺めなどいたるところにある。今はないが、旧東飯能駅西口の桜や丸広百貨店裏の楠木の巨木など心地よいアイストップであった。また、市街地から見える奥武蔵連山もその一つだ。こうしたアイストップをデザインすることで、町や住まいに快適さが生まれる。
天覧山の東側の新しい道からは、加治丘陵につながる新緑に囲まれた飯能の市街地が見える。18年度に、この道は中央公民館前につながり、飯能市街地を通らず入間市方面に抜けられる予定だ。現在はこの中央公民館が、大通り商店街からのアイストップになっている。そこで、道路の拡幅にともなうこの周辺の将来の計画では、飯能河原から遠く奥武蔵連山の四季の移り変わりが大通りから望められるような建築になることを提案したい。飯能らしい絶好のアイストップなのだから。
|
この4月1日、飯能市が宣言した“森林文化都市”は森林と人とのより豊かな関係を築く、まちづくりへの決意と言える。これまでの経済林としての林業経営から環境林としての新たな森林経営を山と町の双方で取り組むことが欠かせない。森林の持つ多様な価値を生かすためにも、杉・桧の単純な山から広葉落葉樹を加えた複層的な山への移行が大切だ。その過程で、これまでの歴史や文化遺産を大切に生かしながら、エコロジカルかつエコノミカルな“西川地域”がつくれたらすばらしい。
高齢化やストレス社会の中で、森林セラピーは森の癒し効果を生かした医療と地域づくりのヒントになる。日帰り森林浴や木材チップの裸足コースなどはすぐにも出来る。将来的には森林保養地、宿泊施設、レストラン、森林散策路、作業療養師の学校、治療コース、薬草の薬局、森のスポーツなどが考えられる。森林セラピーは森の整備・管理・保全にもつながる。6/12午後、はんしんホールで森林セラピーの講演がある。森林セラピーは森を知り、人と森のあるべき姿を考える良い機会と思う。
|
国道299号線を正丸峠の手前、天目指峠への入り口に旧南川小学校はある。明治7年に正蔵庵で南川学校として創立した南川小学校は、明治37年築造の平屋と昭和12年築造の2階建ての校舎が現存している。前者は県内でも最古の部類の小学校建築であり、全体的に質朴堅牢で玄関の車寄せ部分に漆喰塗彫物が施されている。後者は玄関周りの外壁がモルタルで重厚感がある。2階から裏山への避難用の渡り廊下は県内でも例を見ない。平成5年3月31日吾野小学校との統合により閉校した。
ところで、広く市民に親しまれているものや、デザインがすぐれているものを対象に、建築後50年を経過した建築物などのゆるやかな保存のために登録文化財制度がある。これは指定文化財と違い、外観を大きく変えなければ、改装してレストランや資料館、ホテルなどに自由に使うことができる。旧南川小学校は身近かな文化財として残して活用したい地域の宝と思う。是非、飯能市で国への登録をお願いしたい。
|
飯能市内に西川材を使って地元の大工さんに家を建ててもらうと、建て主に20万円までの補助金が市から交付される制度がこの4月から始まった。この制度は西川材使用住宅のPRと地場産業の活性化を目的につくられ、今年度500万円が計上されている。リフォームにも5万を限度に補助。構造材や内装材やウッドデッキなどに西川材を使った証として、製材所の出荷証明が必要となる。
木材の流通は大変複雑で、「誰さんの山の木を使った」と顔の見える西川材を使うことは意外と難しい。外国産材が8割を超え、山の手入れが出来ない現状を考えるとこのまま放置できない。本来、無限の木材資源を供給する林業は“木を伐ったら植える”ことを繰り返し、その過程で山の自然環境を維持してきた。そこで、山の登録制度をつくり、その山から搬出したと判る山主にも建て主と同様の助成ができないだろうか。こうした助成が良質な住宅づくりと山の荒廃防止に役立ってほしい。
*問合せ先/飯能市役所 市民生活部農林課 電話:042-973-2111
|
小さな“木の家”は駐車場をあきらめる代わりに、既存の草木をできる限り生かして新築した。建て主の自然や動植物を大切にする気持ちからだった。1年目の夏を迎え、岩沢区画整理地区内のまだ舗装されていない道端で、家を抱きかかえるような小さな庭は潅木や草花でいっぱいだった。鉢から開放された紅葉は、この暑さの中も深い緑の葉をつけていた。居間の窓辺のコスモス越に変わり行く家々が見えた。帰りがけ、玄関脇の日除けに植えたゴーヤをもぎ取ってくださった。
草取りや木の手入れの大変さ、市街地では庭より車のスペースの確保などで、庭が敬遠され勝ち。庭の大切さは、家庭という漢字が“家と庭”でできていることでもわかる。家が生活の器とすれば、庭は生活の潤いと思う。庭の贈り物は生花、果実、見る楽しみ、鳥のさえずり、目隠し、日除け、風除けなど限りない。これを楽しむ“ゆとり”を持つことが今の家庭に欠けている。10軒の家には10の庭があってよいと思う。この秋、我が家らしい庭を考えてみてはいかがですか。
|
墨付けと刻みを工場でするプレカットの使用は、現場に建て始めるまで大工さんがいらない。工務店にとっては大きな作業場が要らず効率的であり、建て主にとってもコストダウンができる。しかし、木を知る機会や大工技術を持たない大工さんの増加は、階段を作れない大工さんなど、家の維持管理を出来にくくしている。現在、体育館や大規模建築が木造でつくりやすくなった環境下で、プレカットの使用はハイテク技術を必要とするこうした建築に最適で、間伐材の活用と合わせて期待したい。
メンテナンスをしないで済む、長持ちする家はない。生活に応じた手直し、時々の修繕・リフォームをして住まいやすくすることで、百年の長持ちが可能となる。そこには身近な大工さんが欠かせない。一本の木が柱や梁となり、建て方の最後に棟が上げるまでの経過とその仕事振りとを見ていると、大工さん達に自然と感謝したくなる。こうした日本の“木の文化”の担い手である伝統の大工技術はローテクだが、歴史的な裏づけのある匠の技であり、次の世代へ継承したい。
|
近年、特に都市部では上棟式を行わない人も増えている中、大工と鋸の目立て職人の両親を持つ山口さんは古式に基づき上棟式を行った。ここ双柳は苗木の産地。それが育林された東吾野の山から杉・桧を秋伐りし、2年間の自然乾燥を経ての建前だった。幣束(ヘイグシ)3本と破魔矢を棟に飾り、餅や御ひねりがまかれた。関係者や声かけしたご近所の子供から大人までが喜ぶ姿に、施主と現場で働く人との連帯感が生まれたと思う。その後、現場に行った時にも話が弾むことになった。
上棟式は工事途中に、建て主が職人へ感謝と工事の安全祈願をする節目の祭事。工事に関わる人が一同に会し、お互い協力して良い家をつくろうという意思確認の場でもある。確かに手間やお金がかかることは事実。しかし、これから自分達が一生を暮らしていく家が、沢山の人でつくられて行くことを通して、人と人とのつながりや心の豊かさを育んでいく。こうしたことが家族の絆、地域のコミュニケーションにもつながる。そんな視点から「上棟式」を考えてみてはいかがでしょうか。
|
かつて、中秋の名月を眺めた縁側は内部とも外部ともつかない日本的な空間。高床の建物や竪穴住居の床がだんだんと高くなり、床に上がりやすくするため、また、立派にみせるために縁ができたといわれている。始めは建物の外側に張り出した形のぬれ縁、やがて内部に取り込まれ内縁ができた。内縁は入側縁とも言われ、外側に雨戸などの板戸、内側に障子をいれ広縁となった。こうした内外をつなぐ縁側は多様な使い方をされるようになっていった。
冬の縁側は日向ぼっこや物干し場であり、断熱空間の役割も果たしていた。夏は座敷への日差しをさえぎり、スイカの種飛ばしをする子供の傍らで将棋に興ずる大人の社交場。また、一人静かに庭を見ながらボーとする思索の場でもあった。幽玄な和の空間に、縁側で反射し障子で拡散された光の演出がある。こうした多用な縁側の消失は内外を遮断したアルミサッシの出現で加速された。今一度、縁側の役割を見直すことで、身近な人や自然との関係を大切にした住まいを考えたい。
|
この夏のクールビズなど、省エネ商品が注目されるのは、地球温暖化を始めとした環境問題にとって良いことだ。そもそも、1950年頃の中東の大油田の発見が今日の石油文明の源となり、便利さと経済性の追求による大量生産・大量消費が、子供から地球自身までをも生き辛くしていると思う。これからの省エネは、消費者に多少の不便さとそれを楽しむ生活術を求め、また、生産者にアスベストなどのように将来に禍根の種を蒔くことがあるという意識をもったモノづくりを求めている。
そして、持続可能な社会システムをめざした省エネを考えるとき、そのモノの生産・使用・廃棄時のエネルギーと環境負荷の総量での判断が求められる。数億年かけてつくられた原油を一瞬にして消費する石油製品に比べ、50年程のサイクルで再生できる木材を樹齢以上使える製品開発に知恵を絞ってほしい。そして、最終的に安全な土にもどれることが一番の省エネだし、環境にやさしい。衣食住の中で“もったいない”と言えるヒトとモノづくりが私たちの価値感を変えていくと思う。
|
近頃、漆喰や珪藻土の左官壁が見直されている。建築基準法でも耐震的に見直されて、土壁は以前の3倍ほどの強さに改正された。川越の蔵造りの棟札に、左官職人の名が中央に書かれているのを見ると、大工棟梁より格が上であったことがわかる。また、職人自らの手のひらでこすり仕上げた土蔵の漆喰壁の鏡のような光沢に、見とれてしまったことがある。新建材によるシックハウスや環境問題から左官仕事が注目されて、左官職人の技術が再評価されるとうれしい。
左官職人の指導の下、建て主やその仲間が参加し、珪藻土や土壁作りなど行うことがある。また、私の設計で、マンションリフォームの内壁を珪藻土で施主の主婦がすべて塗ったり、店舗や社務所の土間に素人が小石を埋め込んだりしたことがある。素人が参加できるのも左官仕事の面白みだが、一人前の職人になるには年月が必要で奥深い。なかなか技術の伝承がされないのも現実。ドイツに見られるようなマイスター制度のような職人を育てる仕組みが法律でつくられることを望みたい。
|
昨今にかけての耐震強度偽装事件や東横イン偽装問題をきっかけに建築士のあり方が問われている。建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めた建築基準法に従い建築をつくる“建築士”は昭和25年の建築士法でその資格が定められている。現在の日本では試験に合格すれば建築士として仕事ができるが、仕事量に対して建築士の数が多い。今回の事件は施工者からの仕事に頼る建築士や建て主のエゴに追従した関係者が将来のビジョンを欠落したことでおきた事件と言える。
建築士法は資格法で業務法ではない。医者や弁護士のような倫理規定がなく、国際的な建築家法が日本にはないため“建築家”が定着していない。本来、建築家は社会・建て主・施工者・同業者に対する道義的責任がある。そして、快適な住環境をつくる大切な職業。私は設計者の最低限のモラルとして、施工者から仕事を、施工者やメーカーからリベートをもらわないと決めている。建て主の要望に適った素材の選定と施工から離れた中立の立場で仕事をすることで存在したいから。
|
抽斗や戸棚が段板の下にはめ込まれた箱階段には、昔の町屋の生活美がある。また、その細部にいたるまで工夫が施された建具や手摺には、無垢の木ゆえの経年変化による存在感や味わいがある。最近の階段は既製の部材で組み立てられることが多く、熟練した大工さんを必要としないために経済的であるようだが、こうしてできた階段は画一的で面白味がない。階段は、しばしば映画の見せ場として登場するように、住まいの一階と二階を結びつける見せ場として大切な要素である。
そこで設計では、階段を建物のどの辺りに設け、上下階の何処を結ぶかを考えるながら、その形状と材質や勾配、幅、手すりの高さなどを決めることになる。たとえば、階段の踊り場に机・手摺に本棚、吹抜けの階段やロフトへの梯子段などに創意工夫をすることで、生活にリアリティを生み出せると思う。また、バリアフリー住宅では段差をなくしたがるが、元気なシニアづくりのために床が段差だらけの住まいを国では研究中だ。階段を考えることで生活のリアリティを取り戻したい。
|
電子顕微鏡で拡大した、木材の一つの細胞写真を見た。細胞壁や膜孔(水や養分の出入りする細胞膜の穴)がはっきりわかる。その細胞の構成を知って驚いた。そこで、ビール瓶と同じ太さの材木を1千万倍に拡大するとその断面は日本の国土の広さとなる。一つの細胞の大きさは日比谷公園ほどで、細胞壁の厚さは公園の周囲を取り巻く数十メートルの道路幅に相当する。セルロースとリグニンでできている木材の細胞壁の構成がすごい。鉛筆ほどのセルロースがリグニンで固められて、丸柱のようなミクロフィブリルとなる。それがおなじ方向にリグニンで固められて層を形成。次々に違った方向の層が幾重にも重なりながら道路を形づくっているという。
木は太陽のエネルギーで大気中の二酸化炭素と地中の水分で成長し、酸素をつくる。人間同様に細胞でつくられている木材を見たことで、あらためて親しみを感じた。そして、セルロースやリグニンの研究・開発がすすめられている現在、無限の資源である木を、もっと幅広い分野で活用してほしい。
|
かつて、向こう三軒両隣の日常的な付き合いができていた頃の住環境の安全・安心は、互いの干渉を好まない住まい方から消えてしまったように思う。耐震強度偽装事件や阪神大震災などの心痛な出来事を通して、マンション住民の連帯感や被災地に互助の精神が起きたことは皮肉だ。また、昨今のニュースで取り上げられる子供たちの身に起こる犯罪などを思うと、人との関係を大切にした快適な住環境づくりに、二百年前に英国で起きたコーポラティブハウジングが参考になる。
日本では1965年前後から直接参加型で行われて今日に至っている。住居を買うのではなく、自分たちの暮らしに適した空間を自分たちで考える集合住宅で、当初より家づくりに関わるため適切な価格で質の高い住まいが確保できる。また、住む前からの仲間づくりが良好なコミュニティや住宅の社会スットクを形成する。名栗の木の家に住む会(13で記載)の“川の見えるプロジェクト”はこうした考え方を取り入れて現在3軒の“木の家”ができる。
|
木には香りがある。建て方を見に来られた方が、木の香りがするので現場が近いと思ったと言う。家をつくるとき、杉、桧など木の特質を生かして使う。浴室の内装を青森ヒバにすると、鼻を突くほどの香りに驚く。塗装せず無垢材の私の事務所も今年で15年になる。来訪者には木(杉)の香りがするとよく言われるが、慣れてしまった者は気づかない。日差しで暖められた杉の床板を雑巾掛けした時など、ふっとした折に木の香りを味わえたりする。五感の中で臭覚は敏感で、鈍感で、慣れやすい。
木の家には香りがある。1年点検で訪ねたお宅で、小学生の子供さんが学校で「何々ちゃんは木の匂いがする」と言われたと話してくれた。思わず私も、設計の依頼主に「吉野さんからの手紙を開封したら、木の香りがして驚いた」と言われたことを話した。香りには癒し効果もある。森林浴と同様に、無垢の木の家のすがすがしさや安らぎを感じるのはそのためだ。同じなら、新建材より、木の香りのする空間で生活したい。
|
住宅の建具を引戸とドアのどちらにするかで、暮らしも変わるものだ。かつて、「日本の住まいは夏を旨とすべし」と言われた。蒸し暑い夏の通風のためには、開け閉めのはっきりしたドアでなく、何処でも開閉位置を決め、通風調整のできる引戸が最適だ。また、間仕切の戸をはずし開放的な大部屋として暑さもしのげる。さらに、取り外しのしやすさから夏の簾戸と冬の板戸と季節で衣替えをした。引戸は床で支えるため、堅牢さから開放された。その極致が障子。まさに日本的な建具と思う。
欧米の壁構造の家にはドアが似合う。開閉スペースが必要なドアは、広い部屋に適する。また、丁番で吊るので頑丈さが必要なうえ、その機密性の良さからプライバシーの確保に役立つ。しかし、歴史的に個人主義の確立した欧米と違い日本でのプライバシーの偏重は家族の気配を感じにくい住宅を生み出していると思う。冷房に頼らず自然の風を生かす省エネ住宅に努めたり、開放的な空間を考えたりしていると、暮らしを豊かにするヒントが日本建築の多種多様な木製引戸にあることがわかる。
|
山を背負った市街地や身近な自然のある飯能が好きだ。が、気になることがある。市街地のシャッターの閉じたままの店や更地、歴史を感じる建物や場所が、いつのまにか駐車場や軒を連ねた建売住宅になっていることだ。将来の町のビジョンが具体化できないと、町の日々の変化の沈殿から生まれる“らしさ”はより低次元に向かう。資産価値を高めるには、誰もが“住みたい町”をつくること。それには、経済的採算性優先から快適な住環境づくりの家造りをする責任が当事者に求められる。
市街地は家という細胞の集積と考えると、新建材でなく無垢の西川材で家をつくることで、家族の健康や林業の再生、職人技術の伝承に貢献をするか計り知れない。そこで、市街地に西川材で100年持つ木の家をつくることを提案したい。具体的には、住まい手の勉強会や土地探しから始まり設計へと進み、山から西川材を伐採・乾燥・製材・刻み・上棟・完成へと住まい手と造り手の顔の見える関係で木の家をつくること。(61で記載)のコーポラティブ住宅もこうした手法の一つの参考となる。
|
9月1・2日に駿大・地域フォーラムの金山町の地場材によるまちづくり研修ツアーに参加。金山町は岩手と秋田に接する山形の7千人程の小さな町だ。「誰もが住みたくなる町、住んでよかったと感じられる町」を目指し、昭和32年の地区巡回懇談会からはじまり「街並みづくり100年運動」「街並み景観条例」へと進み、現在は地元の金山杉と金山大工による真壁の金山住宅の美しい街並みとなる。そして、目立たせず風景に溶け込ませた公共建築、木造りの橋やストリートファニチャーに地元の金山杉を徹底して活用することで、林業・工業・観光・商業の活性化を実現している。
こうした地域づくりの背景には、1878年7月この地に立ち寄った英国人イザベラ・バード女史が見た金山の自然の美しさと人情の温かさのある町を受け継ぎたいという官民一体の思いと、高い意識と自主性の養われた住民の存在がある。そして、金山杉で100年持つ住宅をつくることが健全な「山と町」の基本であるという信念と、時の行政や経済の動向にブレない仕組みの両輪があることを学んだ。
|
全国的に知られる人口7千の金山町のまちづくりを、そのまま飯能には当てはめられないが、100年先を見据えたまちづくり運動は見逃せない。現在、飯能の山は荒廃し市街地は商店街の空洞化で、飯能らしさが消えてゆき美しい景観とは言えなくなった。飯能市が宣言した“森林文化都市”は、森林の宝をまちづくりに生かすことで実現すると思う。そのためには市民と行政が、森林と人間との豊かな関係を築くことを共有することができるか否かにかかっていると思う。
家庭は国家の、家は町の細胞と言われる。毎年、飯能で建てられる500軒前後の家を、すべて西川材で造ると、15,000m3ほどの木材を使う。無垢の西川材で100年持つ木の家は、家族の健康や林業の再生に貢献し、地域経済を活性化する。この実現には、新しい森林活用組織と意識を共有できる人のネットワークが不可欠だ。地球規模の環境的視点と地域の文化的視点で、生き残るための地域づくりが求められる時代となった今日だからこそ、その可能性が出てきたのではないだろうか。
|
和の空間をつくる障子も、紙の張替えが面倒と敬遠されがちだ。子供の頃破ると叱られた障子も、張替えのとき指で穴を開けるのが楽しみだった。当時、障子紙の幅が決まっていたので、桟もそれに合わせてデザインされていた。そして、ホコリがたまらないように下から上に張った。今日、一枚で貼れる紙が市販されているので慣れると簡単に貼れ、木の桟と白い紙の幾何学的なデザインも自由にできる。障子は紙を張替えるだけで部屋をリニューアルさせることができる。
障子の役割は多彩だ。障子は反射と透過を持ち合わせ持ち、吸湿性、保温性、適度な換気と浄化をして、快適な空間をつくる手助けをしてくれる。日差しをさえぎりつつ光を取り込み、均一で柔らかな和の空間も提供してくれる。夜は電灯を反射させ部屋を明るくし、冬は暖かく、夏は涼しく省エネだ。雪見障子越に見る坪庭や西日に映し出しされた障子の紅葉の影絵を美しく思う。こうした日本建築に欠かせない障子を和洋にとらわれずに生かしたい。
|
夏が高温多湿な日本で100年持つ住宅の原型は、無垢の木でつくる日本の伝統建築な真壁の家にあると思う。今日一般的な構造を隠してしまう大壁の家と違い、真壁は柱・梁が見えるので、建てた後の適切な維持管理や増改築がしやすく長く持たせることが可能だからだ。また、住まいは生涯を過ごす生活の場なので、家族構成の変化に対応し、家族の歴史を積み重ねながら完成していくもので、入居時が始まりと思う。
1992年以来こうした考えに立ち、素木の会(⑦と⑨で掲載)では住まい手とつくり手の顔の見える関係で、西川材を使った50軒を越える真壁の“木の家”を実現している。こうした実績により、埼玉県の「木のある生活空間づくり事業」の助成を受けて小冊子ができた。西川材を使った“木の家”の実例写真と“木の家”のつくり方を双六にしたものだ。この正月に楽しんでいただきたい。小冊子(無料)はテレビ飯能(042-974-3611)または創夢舎にあります。
|
最近のニュースに家族間で起こる悲惨な事件の多いことが気になる。核家族化や生活の多様化や個室の充実は、家族同士の一緒に過ごす時間を少なくしていると思う。家族がふだん居る部屋(場所)を居間(リビングルーム)と言うが、半世紀前の茶の間は家族の集まる場であった。そこには火を囲んで語る囲炉裏傍があったり、丸座で食事をするちゃぶ台があった。また、子供の日には子供の背丈を刻む柱や、家族の歴史とともに味わいを深めることのできる無垢の木の家があった。
「家族が一つ屋根の下で暮らす」とはどういうことかを考え、居間の設計はすべきだ。私は居間を家族室と図面に書く。住まいの中で、寝室や台所など用途がはっきりしているのに比べ、居間ほどあいまいな部屋はない。時と共に変化し誕生と死を繰り返す家族関係を受けとめ、居心地の良い居間とすることは難しいが設計のし甲斐があるというものだ。居間で何をするか、何もしないことを含めて、を考えると、家庭の数だけの居間があってよいと思う。
|
都市計画地図の市街地に空き地と駐車場をマーキングして、その多さに驚く。その活用の仕方如何で、将来の町の住みやすさや美しさが変わってくる。高齢化に伴ない老夫婦や単独の世帯の増加で、家族が使わなくなった部屋の活用・老朽化した家の維持管理・病気時の対処などの出来る住まいづくりの仕組みが欠かせない。家族のあり方や生活の仕方が問われている現代、血縁にこだわらず、豊かな人間関係や身近な住環境を大切にしながら暮らしたいと考える人も少なくないと思う。
気心の知れた者同士で、生活の一部を共有する住まい方として、北欧を中心に発展したコレクティブハウジングは地域づくりにも役立つ手法だ。日本でも阪神大震災の復興時に実現している。自分や家族の生活は自立しつつ、家事労働の分担のできる台所やコミュニティのサロンなどを共有し、お互いに助け合いながら暮らすための家づくりだ。そこで、住まい方や暮し方の勉強をしながら、診療機関との連携やシックハウスを誘発しない地元の西川材を使ったコレクティブハウジングを提案したい。
|
時を蓄積した里で知られる金山町(65で記載)杉沢村で、1994年より毎年哲学講座を続けてきている内山節さんの講演「森を考える」が、駿河大学の公開シンポジウムで行われた。
森林の機能性や経済性が重視される今日、死後の魂が森で浄化され山の神となった時代の森と人間との神仏的なつながりを忘れていると言う。西欧の人間中心的で合理的な思考と違い、自然をありがたいと同時に災いをもたらす存在として、上手に付き合ってきた日本人の歴史観の話に共感した。
また、本来の日本の山は草原の先に森があり、生物世界も多種多様であった。近年の森の増加と草原の減少は、特定動物の増加や夏の昆虫の減少を招き生態系も崩したと話された。西川地域の森を感じ、生き方を考えながら森林を再生することが大切。具体的な方法として、自分の地域の中に入ってきたお金を出さない地域づくり、山の仕事や大工をめざす人を3年間位支える仕組みづくりが必要との助言。人間と自然を結ぶ森林を育てていくことが飯能らしい町をつくることになると思う。
|
土間は竪穴住居の大地のイメージ。北方系の竪穴住居と南方系の高床住居の融合が日本建築の原点と思う。伝統的な民家には炊事や雨天時の野良仕事をする土間があった。赤土、石灰、砂に苦塩(ニガリ)の三和土(タタキ)の土は生活の歴史を刻みつつ太古の懐かしさを感じさせる。
土間は近隣社会と結びついた場でもあった。その名残である今の玄関は出入口だけの狭い処となるが、土間を設けることで、家族や他者とのコミュニケーションの場をつくることができる。
私の設計した、八角土間の家は普段は玄関と応接を兼ねた土間でホームコンサートを開いた。仏子の家は薪ストーブのある土間がソバ打ちや家族や知り合いとの団欒スペース。黒磯の家は玄関を入ると台所と囲炉裏のある土間で来客を迎える。笠縫の家は趣味のバイクの作業場を土間としている。こうした家に共通していることは、靴を脱ぐだけの場になってしまった玄関を、それぞれの暮らしにあった土間とすることで、家族関係や近隣関係を豊かにしてくれるスペースに変えていることだ。
|
地球温暖化は人間活動によるもので「今後確実に進み実害に直結する」と、政府関係者と世界有数の科学者によるIPCC(気候変動に関する政府間パネル)が07年2月に結論づけた。シナリオの違いによって、1.1~6.4℃程度の気温上昇の幅はあるが、今世紀中に地球の平均気温が最悪の場合6.4℃程度上昇するというものである。平均気温2℃の上昇で動植物種の2,3割が絶滅すると予測されるなか、変化が顕著になってからの温暖化対策は手遅れとの報告は深刻だ。
地球温暖化の危機を最小限にできるのは、私たちの日々の小さな取り組みからと考える。先に観たゴア副大統領の映画「不都合な真実」でも、“私にできる10のこと”を掲げ、今ならまだ間に合う最後のチャンスと訴える。そこで、現に住む家の省エネは当然だが、家の製造と解体にともなう石油製品や化石燃料の削減を視野に入れたい。“木の家”は、太陽エネルギーで二酸化炭素を固定した木材でつくられ、木は土に戻る持続可能な循環資源で、地球温暖化に貢献大である。
|
人は緑に集まり癒される。木から出るフィトンチッドや酸素が人に安らぎを与えてくれるからだ。そこで、緑に抱かれた市街地をつくるために、スーパー・商店・事業所・個人の駐車場に車の台数分の木を植える。未利用地は広さに応じて木を植える。敷地周りのブロック塀やアルミフェンスを生垣にする。建物の外壁や屋上を緑化する。店先や路地を植栽や植木鉢で飾る。広がりのある歩道にはベンチを置き、木を植える。こうした“市街地の杜”が市民と行政で共有できるとすばらしい。
例えば、植える木は山主の協力を得て山に自生する木を入手し、ボランティアで市民や地主が植樹や、落ち葉など日常の手入れを行う。高木になったら、街路樹のように剪定などを行政が手助けする。木々の成長につれて、四季の変化を感じながら街歩きの楽しみも増すことだろう。この“市街地の杜”づくりは、地元での買い物客や観光客を増やし市街地の活性化につながる。また、市街地に木を植えることで、地球温暖化対策や森林文化都市の具体策など多彩な効果が期待できる。
|
「和室」という言葉が定着したのは戦後で、椅子に座る生活を基本とした洋室に対比した言葉だ。戦前の畳敷きの部屋は「座敷」、「茶の間」、「何畳」などと呼ばれ、障子、襖などの間仕切りの建具を取り外すと、使い勝手に応じて部屋の広さが調整できた。戦後の生活様式の変化が畳敷きの部屋を個室化することで「和室」と言う言葉を生み出したとも言える。さらに、今日の生活は「和室」に多様な家具を持ち込み、すっきりとした畳の良さをなくしてしまった。
最近「和室」のない家もあるが、畳や床に直に座り、くつろぐことの精神的な側面を呼び戻したい。木造を基調に、畳、厚床板、障子、襖、床の間などの伝統的な手法は参考になる。畳や杉の厚板に座って見る庭先の風景。障子を通した柔らかな光。足元や枕元を通る風。襖や板戸による空間の自在性。椅子座と畳座をつなぐ小上がり。十分な収納を確保した清楚な生活空間。使用目的でしつらいを変える床の間。自然と人間の共生した暮らしの手がかりを見つけることができると思う。
|
市街地や山里で空家を見かけることがある。家は人が住まなくなると傷みも加速する。空家は身近な安全安心のバロメーターで、一軒でも少ないほうがいい。そこで、地元の西川材で家をつくる住まい手に、工事期間中の仮住まいとして、市で空家を借家に提供する
“木の家づくりヤドカリ制度”はどうだろうか。現在飯能市が行っている西川材使用住宅の補助金(51で記載)と併用することで、西川材の家が造りやすくなり、森林の保全や大工技術の伝承や地域経済に役立つと思う。
建築的にも価値のある民家や商家などの空家は、当時の住まいや暮らしのエキスが詰まっているので、直接生活体験できる滞在型施設が有効だ。また、林業体験や自然体験、他所から市内の視察や調査などに来られた方の休憩や宿泊としての利用も考えられる。さらに、市内各地のエコツーリズムと組み合わせると地域づくりの効果も期待できる。身近な一軒の空家の活用を、市民と行政で話し合うことから始めよう。空家を地域の魅力的な場に変えるために。
|
夏の猛暑が当たり前になってしまった昨今、エアコンは必需品だ。その使用は廻りめぐって地球の温暖化を促す。しかし、今年の異常な暑さの中、エアコンを使わずに過ごすことは大変だが、設定温度を28度以上にすることで温暖化防止の一助となる。さらに積極的にエアコン無しの生活をすることがベストだ。この夏、一年点検で訪ねた山口(54で掲載)さんの家はエアコンを使わない生活を実現していた。“木の家”を緑の日除けで覆って。
よく見ると、道路際の車庫はアサガオ、その軒先から玄関の庇へかけてヘチマが簾状に続く。暑い日が差し込む南側、母屋2階の4間のバルコニー下一面がゴウヤで覆われていた。室内の居間や和室から見ると重なり合った葉越しの日差しは柔らかく、居間の濡れ縁で取り立てのキュウリも食べられたとのこと。西側の日除けにはキュウリがまだなっていた。ゴウヤは手入れも簡単で、葉は美しく日除けとしてぴったりだ。来年、是非試してみたいと思った。
|
公共建築はその場所やその時代の文化水準の指標となると共に、一般の建築の模範となるべき存在と思う。萩市では公共施設に、点在する萩藩(長州藩)以来の木造建築を活用していた。歴史と風土が身近に感じられる町並みを観て、そこの文化の高さを感じた。日本では法隆寺を筆頭に歴史的木造建築を残して来たが、現代のコンクリート建築は半世紀足らずで矢継ぎ早に建て替えられている。コスト優先の現代の公共建築がどれだけ後世に残るだろうか。
日本の木造建築は戦前まで、気候風土に適った進化をしてきた。伐採した木の樹齢以上に建築を長持ちさせ、その間に木を育てることで、大気中の二酸化炭素を増やすこともなかった。森林文化都市を目指している飯能市では、森の恵の木材を使い、地元の大工技術で率先して公共建築を造ってほしい。築40年のコンクリート造の名栗小学校を木造で建て替える計画が進んでいる。これに続く公共建築が百年先を見据えた木造建築で造られるなら、他所にはない飯能らしい町が実現すると思う。
|
伝統建築は、地場の木を使い地元の大工さんがつくる地産地消でエコロジーな建築だ。適切な維持で百年持たすことができる。地震国の経験を踏まえて、建築全体で地震力を吸収する柔構造。その反面、戦後の建築は地震の度に耐震壁を強固にしてきた。近年、伝統建築の耐震性が再評価され、石場建ての土壁の家も限界耐力(36で記載)で設計可能となった。しかし、耐震強度偽装事件による建築基準法の改正(2007.6.20)で確認制度の垣根が高くなり、伝統建築が危機にさらされている。
そもそも、建築は各国固有の文化だ。建築を耐久消費財と考えた戦後の経済至上主義は、自然や風土の豊な日本の個性的な町並みを金太郎飴のように何処も同じ町に変えてしまった。今、“伝統建築をどう伝承するか”の視点が重要な時期と思う。この改正で確認の申請側も審査側も戸惑い、業務が滞り、経済に影響が出始めている。この先、建築文化の停滞も予想される。建築家法(職能法:58で記載)のない日本の現状を憂いつつ、伝統建築が地域に当たり前に存在することを願う。
|
今年は子年。おとぎ話のなかで鼠のくわだてで十二支からもれた猫は、居心地のよい処を見つける才能を身につけ、人間とも付かず離れずいるのだろうか。冬は陽だまりや暖房器具から程よい場所に、夏は日差しを避け風通しのよい場所にいつの間にか寝転んでいる。人間も子供の頃は居心地よい処を見つける天才だ。誰にも邪魔されない秘密の場所を、納戸や土間の片隅、時には屋根裏や押入の中に見つけたものだ。そこは遊び場であり、小宇宙であり、創造力の源であったように思う。
“居心地がよい家”ってなんだろう。旅から帰ったときのあの安堵感もその一つ。これからの生活をささえ、環境とともにあって、くつろげる家をつくろうとした時、山に入り、植林し、育った木を見ると、誰しもこの木で家をつくりたいと思うのではないだろうか。寝転んで眺める、天井や壁の木目や何気なく触る床の感触。何も考えていないようで、何かを考えている。ボーッと外を眺めながら感じる、家族の気配や木の香り。新しい年を迎え、子どもの視線にたって考えてみたいものだ。
|
気づくと、ものが溜まっていく今日の暮らし。何を捨て、何を買い、何処に収納したらよいか悩みは尽きない。収納の設計は暮らし方を見つめることから始まる。片付いている状態と使いまわしていく場面とをうまく組み合わされていくことがポイント。日常ものと季節ものとを区別し、使う場所に使いやすいように片付けられることを心がけ、小物の収納から各部屋の造り付け家具やロフト・床下・間仕切りを活用した空間収納へと設計を進めていく。
温暖化問題による環境の変化や製造・使用・廃棄時の二酸化炭素の削減は、産業構造や生活様式の変化をもたらすだろう。暮らしの変化に対応する収納を考えることは今日的な課題だ。かつての和室と押入のように、寝具を押入に仕舞い込むと、寝室から居間にも、食堂にも、客間にも変わる融通性のある関係を、新しい生活スタイルに応用してもおもしろい。また、これからの収納を考える時、もったいないと思う心と、捨ててよいものを見抜く目で、ものと付き合うことが必要と思う。
|
樹木は、活発に成長する春と活動を休止する秋によって年輪ができる。四季のある日本で、しかも杉など針葉樹の年輪はわかりやすい。同じ4寸の杉丸太でも、5,6本の年輪から200年を超える杉の木まであることに驚かされる。年輪の幅は成長するにつれ狭くなり、また、南側が広く北側は狭い。木は製材の仕方で、柾目と板目の異なる木目模様をつくり、同じ木目は二つとしてなく美しい。人間は年令に経験を刻み、木は年輪に人間とのかかわりの可能性を刻んでいると思う。
その年の気象条件を忠実に反映する年輪を利用して、年輪年代法が編み出された。これにより、遺跡から出土する木片で、その年代や古建築の年代も特定できる。一つの年輪の材積も、日本全体の樹の材積となると、一年間の日本中の住宅を建てても余る分量がある。木材はすべて国産でまかなえる数少ない資源であるのに、日本の木材需要の8割を外材に頼っている昨今。温暖化防止(73で掲載)のために、もっと国産材の個性を大切に活用したい。
|
伝統構法と在来工法の違いを知らない建築の専門家も珍しくないのは、文明開化で西洋建築の様式や技術を良しとし、それまでの伝統技術を蔑ろにして来た歴史にさかのぼれると思う。地震や台風に対して、礎石に建てた柱を水平の貫でつなぎ、柱と梁を仕口・継手で組む伝統構法は、強靭な建物を造ってきた。昭和25年にできた建築基準法による在来工法は、柱梁間に斜めに設けた筋違や合板の耐震壁で対処している。大地震の度に強固な耐震壁をつくるため、金物を多用することになった。
木と金物は馴染みの良いものではない。木は湿気を保有し金物を錆びさせる。安価に多量に作られる金物の耐用年数で家の寿命が決まってしまう。阪神大震災と同規模の鳥取地震で古い民家が震災を免れたことは余り知られていない。最近の耐震実験により、伝統技術でつくられた建物が地震にねばり強いことが実証されつつある。伝統構法で建てた“木の家”が自然災害、健康、環境に安全・安心な、自然と人間の共生に適った“木の文化”の要にあることを次世代に伝えることが大切な時と思う。
|
永い年月かけて育った木は伐られてから、私達の回りの色々な物に使われ、新たに人間との付き合いを始める。美しく長持ちさせるために木を焼いたり塗装したりするが、木で物をつくる時、時を刻める白木使いが基本と思う。無垢の木は使い方や手入れの仕方で、味わいを深めることができる。拭き掃除だけで光沢の出る床板、民家の囲炉裏の煙でいぶされて黒光りのする柱、世代を超えて受け継がれた仏像や民具や家具などを、目の当たりにすると、木は神からの贈り物と思う。
今日の技術の発達は、木に化学物質を含浸させてセラミック化、不燃化、防腐化した、また木を接着させて集成材や合板などの新建材を生み出したが、その耐久性と安全性が無垢の木に勝るとは考えにくい。無垢の柱と違い集成材の柱は“木”の表面に接着剤を塗り、極薄板で4面を貼り、“困る”という字を連想させる。接着剤で囲われた木は呼吸(湿度調整)できない状態で、今日の暮らしの閉塞感にも通じる。現代社会の価値感の囲いを払拭し、新しい暮らし方を希求する時だと思う。
|
高温多湿な夏の日本で、昔の家は柱間の壁を少なくし風通しを良くしてきた。今の家は壁が多く、窓が小さくなった。また、気密や断熱の施された室内空間は、エアコンでコントロールされて快適だ。しかし、新建材などによる汚れた空気の入れ替えのため、建築基準法で吸気口と換気扇による24時間換気が義務付けられている。こうした家の中にいると、窓の外の世界を一枚の絵のように見ることが出来ても、五感で感じることはできない。
人が住まなくなると、締めきられた家の空気が淀み腐るから、家は急速に朽ちる。毎日、空気を入れ替えることの大切さがわかる。家を長持ちさせるコツは通風を良くすることだ。また、風が通る木の家は、夏の陽射しのなかで木陰にいる心地よさを味わえる。日本人の自然に対する豊な感性は、四季の微妙な移り変わりに身をおくことで、文化を育んできたと思う。青葉の香りや風鈴の音に心を通わせることのできる子どもたちを育てるためにも、“風が通る家”が大切と思う。
|
都市のヒートアイランドや省エネ効果に効果的なところから、屋上緑化が注目されている。冬の保温、防火、騒音の防止、周辺環境への快適性や鳥類、昆虫類の生息回復なども期待できる。日本には古く「芝棟」と呼ばれる草屋根の棟造りがあった。茅葺の弱点である棟部分を補う実用と美しい草花を咲かせ芝棟は、田舎の原風景といえる。現存する屋上緑化として、文京区根津にある朝倉彫塑館(1935年)が知られている。飯能にも、大正後期に建てられた木造3階建の畑屋に、屋上庭園がある。
日中50度以上になる屋上も、緑化すると土壌中は、終日30度以下となる。屋上緑化は、潅木では30cm、芝でも15㎝の土壌と自動潅水が必要だ。しかし、最近は軽量人工土壌や仕組みの開発が進み、保水能力の向上や傾斜屋根の施工もできるようになった。例えば、乾燥に強いセダムだと5㎝以下で、水遣りをしなくても済むという。建築の壁面緑化と合わせて、空中の森をイメージした都市が現れる日も遠くない。また、市街地では家庭菜園や芝生でバーベキューと夢が広がる。
|
7月12日、工学院大学アーバンテックホールで、これからの木造住宅を考える連絡会(6団体)が、「このままでは伝統建築の家がつくれない」をテーマにフォーラムを開催した。法律の位置づけのない伝統構法が認められてきた矢先、耐震偽装で厳格化された基準法が伝統建築を建てにくした。このことに危機感を持った当会と国の話合いで、今後3年間で、伝統構法を建築基準法に盛込む動きとなった。地域性や多様性を失わず誰にでも使える法律ができるように尽力したい。
「今、私たちが先人から受け継いだ日本の伝統的な建築技術を手放してしまったら、百年後、二百年後、この日本から、風土に溶け込んだ美しい風景が、季節のめぐりの中にある暮らしが、日本らしい感性が、失われてしまいます。技術も風景も文化も、そして感性も、いちど失ったら、取り戻すことはできません。日本という国が、歴史や文化、職人技術を尊重し、それを活かすまっとうな国であってほしいと願います。」と、採択された決議文の主文にある。あなたも、一緒に考えてください。
|
木材は乾燥することで、その強さを増すとともに、狂いも小さくなる。家をつくるとき大工さんが最も気にするのは木材の乾燥だ。丹精こめて刻んだ仕口や継手が、緩んでは取り返しが付かない。最近の家は、均一に規格化された集成材や人工乾燥材がよく使われる。繊維質のセルローズを樹液のリグニンが固めている木の細胞(60で掲載)から、水分と同時にこの樹液までも減少させてしまう人工乾燥材。これにノミを立てると、「内部がパサパサして怖い」と大工さんたちは話してくれた。
木材は太陽が育てる無限の資源だ。伐採時の樹齢以上に大切に使うことで、木材は究極のエコ材料となる。木はどれも個性的で、使い方を間違えると短命で“もったいない”ことになる。木材の乾燥は電気や石油で人工乾燥するより、太陽の天日干しが似合う。次の世代に木のある暮らしを実現することが、持続可能な社会の基本と考えられる。そのためには、木材の公的な大型ストックヤードと共に、暮らしの中で木を扱う職種間ネットワークと職人技術の継承を大切にしていきたい。
|
1990年代初めのバブル経済の崩壊で、山の荒廃や雑木林の減少による危機感が表面化した。それらの再生の動きとして、「市民と森林を結ぶ全国のつどい」や「全国雑木林会議」が毎年全国各地を持ち回りで行われてきた。前者は第13回が2008年3月に九州の福岡で行われた。また、昨年石見銀山で行われた後者が、第16回を10月17,18,19の3日間、駿河台大学をメイン会場に行われる。「森林文化都市」を宣言している飯能市にとって、山を含めた雑木林会議が開催されることは意義深いと思う。
17,18日の9つのエコツアーは里山の暮らしや森林体験などができる。18日の午後に、開会式と「武蔵国の平地林と山地林」の基調講演がある。18,19日は中庭で多彩なイベントも行われる。19日午前には、森林の大切さを知る5つの分科会がある。その一つ「山を生かす暮らし」で、生活の基本である衣食住に“遊”を加えた専門家のパネルディスカッションがある。そこに、西川材を使って職人と一緒に百年持つ“木の家”をつくることが、地球温暖化防止に役立つことを提起したい。
*問合せ先/実行委員会事務局 電話:042-972-2560
|
日本の食料は外国頼みで、自給率が4割を切っている。山間部の高齢化で放棄された農地や平地部の休耕地が広がっている。ところで、山の木材資源は完全自給できる森林が育っているのに、木材は8割が外国産材だ。これらを活かす仕事がない現実。また、都市部でも仕事につけないフリーターや高齢者が増えているという。人は誰もが秘めた能力を持っている。これからの農林業の再生は、人間らしい生き方のできる働き場を、人の知恵と創造力を働かせて創れるか否かにかかっていると思う。
山の宝を生かす一番大きな分野は家づくりだ。100年持つ木の家づくりに職人さんは欠かせない。休耕地や高齢化の進む里山の維持が難しくなった田畑を借り受け、自ら耕作して安全な食物を食べ、食費分を伝統技術や新しい技術の習得に向けて自己の能力を生かしたものづくりができるような仕組みを考えてみたい。実際の仕事を通して、住い手と造り手が一緒になって、地元の西川材を使い、地元の職人でつくる“木の家”ができれば、森林文化都市の細胞ができていくと考える。
|
人生の3分の1は寝て過ごす。生活が洋風化しても、寝る場所は欧米のベッドルームと違い、畳にベッドを置いて寝たり、マットレスを床に敷いて布団にもぐり込んだり、ベッドに布団を敷いて寝たりと、住まい手によって様々だ。また、寝る場所は睡眠以外にも個人的行為に使われるプライベートな空間で、人の誕生から墓場までを過ごすなかで、子供室、夫婦の寝室、老後の居室と時々の変化に対応した融通性や快適性が求められている。
そこで、寝る場所の設計には、家族とどう向きあって暮らすかという視点が必要となる。寝る場所と家族の居場所(69に掲載)との空間的つながりを大切にして、広さや仕上げ、洗面やトイレやバスとの関わり、収納の仕方などを考えて見るとよい。また、布団を仕舞うことで多様な使い方のできる和室の融通性や、居間のコーナーやロフトや狭いスペースを活用することで、心地よい空間がつくれたりする。寝る場所を考えることで、家族の関係や画一的な現代住宅を見直すきっかけとしたい。
|
現代の家は、要望を適えようとすると大きくなりがちだ。部屋を広くしても、雑多なモノに囲まれ、手狭に思う時もある。また、普段の生活ができる広さに、来客を迎えるハレの場を別に設けて大きくしても、住み安いとは限らない。家の掃除は広く大きいほど大変だ。ところで、小さな家は経済性や環境に優れている。少ない資源でつくられること、住んでいる時と寿命がきて解体する時のエネルギー消費が少なく、二酸化炭素の削減に役立つことで、地球温暖化防止の一助になる。
小さな家は、小さくとも狭さを感じさせないことが要。大きな家の縮小番にしないことだ。「人間、起きて半畳、寝て一畳」と言われ、2畳に2、30cmの板床があれば、立派な夫婦の寝室となる。また、4畳半のスペースがあれば、3,4人が寝ることも、6人が食事することもできる。小さな家は機能的で、落ち着く空間をつくりやすい。できる所は極端に狭くして、家族団欒の場を広くつくるのもよい。これからの生活で大事にしたいことを見つけることから、小さな家づくりは始まる。
|
文京区本郷の不忍通りより根津神社への路地にある金光教本郷教会と、豊島区池袋の明治通りジュンク堂先の路地にある個人住宅を“木の建築”でつくる。前者は森の中の教会を、後者は都会の中の民家をイメージして設計した。飯能地方の西川材を運び、金物を使わず伝統の仕口・継手による真壁造りだ。新年に竣工奉告祭が行われた教会で、床暖房ような無垢の杉板の暖かさと木の香りに、信者の方々が驚く。共にビル群の中にあって、存在感を保ちつつ、癒しの場を提供してくれる。
木は太陽と土と水で育ち、酸素をつくり、二酸化炭素を吸収する大変エコロジーな素材だ。乾いた木の重さのおよそ半分は、空気中のCO2を炭素の形で固定している。坪当たり1m3以上の木材を使っている二つの建築は、そこで使われた木材のCO2の蓄積量を生きた木に置き換えると、都市の中の森林といえる。使った木材の樹齢以上に“木の建築”を長持ちさせることで、その再建に見合う木を山に育てることができる。飯能市の“森林文化都市”を考える時に、思うことの一つだ。
|
団塊の世代にとって、映画「三丁目の夕日」は子ども頃のノスタルジーを感じさせる。あの頃の“向う三軒両隣”には、夕食のおかずのやり取りも当たり前の家族的なコミュニティーがあった。しかし、高度経済成長による都市への人口流出は核家族化や互助の精神の後退を促し、他人への無関心を生む。人間関係の希薄さから高まる防犯意識は、出入り口の二重の鍵締りや格子や防犯ガラス、警備会社の防犯システムを望ませる。自己中心的な家づくりが、近隣関係を損ねていることに気づかない。
家を建てる時、裏の家の陽射しや風通し、窓の位置によるプライバシーの配慮など考えことは多岐にわたる。美杉台で設計した家の建て方の時、裏の家の方から感謝されたことがある、日陰になると思っていた居間に、陽射しが入るので嬉しいと。こうした積み重ねの中から、本来のコミュニティーがつくられることを願う。少子高齢化が進む中で、地域社会の安心・安全をお金に頼るより、お互いのプライバシーを尊重しつつ、近隣で助け合える“向こう三軒両隣”を見直したい。
|
家は、ハウスメーカーや工務店に一括発注か、建て主の希望を適えやすい設計と施工を別けて発注するかが一般的。双方とも職人との関係は、建て主や設計者にとって間接的といえる。建て主が直接各職方に頼む分離発注や、さらにそれを設計者がサポートする直営工事は、本物の木の家をつくれる職人との直接対話が魅力的だ。数件の経験から施工管理の煩雑さからしり込みしがちだが、コストの透明性や家をつくる手ごたえなど、建て主にとっても有益な家のつくり方と思う。
最近のプレカット(53に掲載)に頼る家づくりに、大工の伝統技術の消滅の危機感を持っている。これまで60数軒の伝統的構法の家づくりを通して、100年以上に家を長持ちさせるためには、職人の技術は不可欠と確信する。建て主の家づくりへの参加を通して、職人技術の次世代への伝承と100年持つ“木の家” (14に掲載)をメンテナンスする地元職人のネットワークの試みが、原市場のM邸で始まった。この直営工事では、山のこと・職人のこと・素材のこと・建て主のこと・設計者のことを考えながら、建て主と職人と設計者の顔の見える関係に取り組んでいる。
|
1950年頃の中東での大油田の発見は、産業革命による手工業から機械工業への社会の変革を飛躍的に加速させた。戦後の高度経済成長は石油などの資源を輸入し、工業製品を輸出して成しえたと結果と言える。そして、今日の大量生産・大量消費・大量廃棄が人類生存の危機を招いていることを、米国の元副大統領ゴア氏は映画「不都合の真実」で語っている。また、昨今の食や住まいの安心・安全の崩壊や世界金融危機が、学び働くことの意味とこれからの暮らし方を私たちに問いかけている。
人間は自然から離れては生きられない。自然と共生したエコロジーな暮らしを取戻すために、生活の基本である衣食住に遊を加えた暮らしを再考したい。そこで、時には講師、時には塾生となり、次の世代に何を継ぐのかを見据えて新しい産業や暮らせる地域を再興する運動として “くらし彩考塾”を提唱したい。この考えに立ち、4月から自由の森学園で講座「森と木の家」を受け持つ。現在の便利な生活を見直し、安心安全な暮らしができる地域となれたら最高だと思う。
|
「身土不二」は、その土地の風土と共に人間存在があるといった仏教用語で、その土地、その季節のものを食べることが身体にいいという明治から大正にかけての食運動で使われた。この身体と環境とは不可分という考えが、今日のスローフード運動の高まりから、食の分野ではその土地のものを地元で使う「地産地消」に定着し始めている。住の分野では地元のものを使った家づくりは稀で、大量生産品の小量が遠隔地から運ばれる建材の家づくりが主流だ。地産地消はこれからの課題と言える。
一軒分で使う材木を、重油などを使う人工乾燥でなく天然乾燥だと、5t前後のCO2の削減となる。九州から運ばれてくるホーロー浴槽をその土地の桧で地元の職人がつくると、生産時と輸送時のCO2は桁違いに削減される。廃棄時のCO2排出もわずかだ。まず、地元の木(西川材)を大切に使うことが、環境と生活を守り、地域経済のためになることを知ることから始めたい。また、地産地消を楽しみながらするエコロジーな生活感を持つこと、育てることが大切となる。
|
日本は自然に木々を育ててくれる風土だ。“木の文化”の国を誇れた頃は、その木を活かした暮らしが当たり前であった。今日、無垢の木でつくられたモノを探すことは意外と難しい。近い将来、石油は枯渇しないまでも、より高価で使いづらくなるだろう。太陽エネルギーで育つ木は、最も省エネなエコ素材で、樹齢以上使えば無限の資源だ。しかも、木は人間と同じ生物で、安全・安心な暮らしの素材と言える。もう一度、木を活かした暮らしを取戻すために「一人一木」を提唱したい。
子どもの誕生を記念して木を植える。木の机や椅子や本棚を手作りする。アクセサリーをお気に入りの木製品にしてみるのもよい。私の携帯に付けた手作りの小枝ストラップは少し艶が出始めた。木へのこだわりは什器から家に至るまで奥深く、愛着を育む無垢材の使用がその要と考える。人に見せたり、売ったりできる“一木”を持つことが、暮らしの中の石油製品を木に変えて、自然と人間を結びつける暮らしにつながると思うからだ。
|
所沢で伝統の仕口・継手による“木の家”をつくるため、まず地元で大工探しをした。10軒近くで造れないと言われ、以前手がけた他市の棟梁に建ててもらう。最近は8,9割の家がプレカット(53に掲載)によるため、階段を造れない大工さんが多くなり技量の低下が心配だ。壊すことはたやすいが、継ぐことの難しさを思う。戦後60数年が過ぎて、全国各地にある伝統構法(83)の家づくりの灯火が揺らぐ。職人の高齢化と共に、その技術を次の世代にどう継いでいけばよいのだろうか。
森林に恵まれたこの国から、当たり前に“木の家”をつくることができなくなることは、もったいないの一言に尽きる。私は木の家に住みたい人と、その技術を伝えたい職人との架け橋となるように心がけて設計をしてきた。直営工事(95に掲載)もその一つ。そして、技術を教えたい人と学びたい人が出会い、若い職人が育つ仕組みで木の家をつくるために、大工職だけでなく建具など他職が同じ理念で集まり、木の建築をつくる取り組みに挑戦したいと思う。
|
ここ数年の間に見た、庭先のブナ・ナナカマド・ニシキギの立ち枯れに、身近なところで地球温暖化を感じる。私たちは便利な生活と引き換えに、地球温暖化による未曾有の危機を背負うことになる。石油は有限の資源だが、木は伐ったらその樹齢以上に使うことで、無限の資源となる。木が自然に育つ風土の日本で、“木の文化”を次世代に継ぎたいとの思いから、森や木のこと、職人と家づくりのこと、住いや設計のこと、まちづくりのことなどを取り上げ、木を大切に活かす暮らしを考えてきた。
山形県金山町(65で掲載)は、時の行政や経済の動向にブレない理念で、金山杉で100年持つ真壁(⑧で記載)の家によるまちづくりを実践していた。「民家こそが、人間と自然を結びつける、非常に重要な接点」(⑤で記載)を実践している町だ。森林に恵まれた飯能も、地域経済と生態系に適い、シックハウスに縁のない、西川材を使って地元の職人さんがつくる100年持つ木の家(14で記載)で、飯能らしい町が実現できると思う。連載の終りに、100年先を見据えて木を大切に活かした町を願う。
|
|